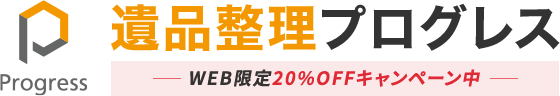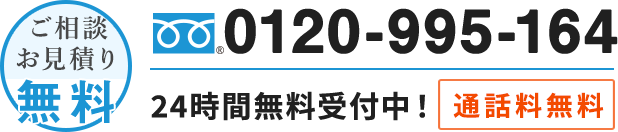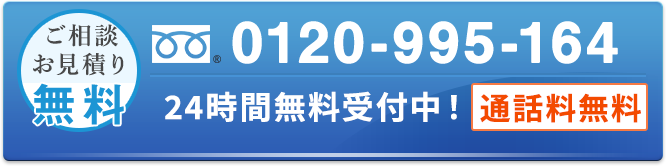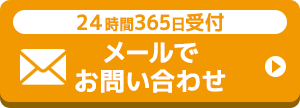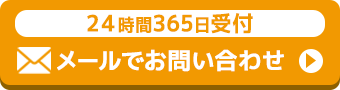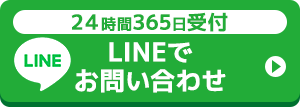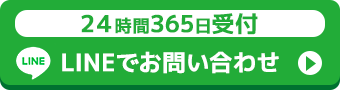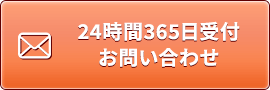遺品整理は故人様が残した愛用品を整理する作業ですが、品物に情が湧いてしまったり処分すべき品の判断が付きにくかったりと、手が止まってしまうことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺品整理で残しておくべき品についてご紹介します。
この記事を監修した人

- 小西 清香氏
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
遺品整理に着手する前にやるべきこと

遺品整理に着手する前には、必ず品物の仕分けを行うようにしましょう。この作業には品物の種類・量を把握することと、エンディングノート・遺言書のような故人様の意思を確認するための資料を捜索することで、整理作業を円滑に進める狙いがあります。
時間の都合でやむなく仕分けを介さずに直接整理に当たらなければいけない場合には各機関への手続きに必要な権利書などの重要な品を処分しないように注意することや、処分して後から後悔しないようにきっちりと吟味することを徹底する必要があるほどに、仕分けと整理をきちんと区別することは大切なのです。
エンディングノートと遺言書の違い
遺言書とエンディングノートは似て非なる存在です。故人様の遺志が記されているという点では同じですが、遺言書には法的効力があって故人様の願いを書かれている通りに実現する義務が生じることに対して、エンディングノートに書かれている要望には法的効力はなく、極端な話をするなら実現できなくても問題はないという違いがあります。
残しておく遺品を見極めるポイント

手元に残しておくべき品と処分品を見分けるポイントは以下の4点が挙げられます。
捨ててはいけない品か否か
現金・レンタル品・エンディングノートに処理方法が示されている品など、捨ててはいけない品を発見した場合はすぐに処理方法を判断せず、一時的に保管しておく必要があります。
相続品か否か
当然ながら、相続品は相続人での話し合いもしくは遺言書に従って正しく相続が行われるべき品です。勝手に持ち出したり処分したりすると他の相続人から着服を疑われたり、悪い場合には裁判に発展する可能性もあります。そのため、相続品と思しき品に加えて、権利書や印鑑など相続に関する品も残しておくようにしましょう。
故人様の息遣いを感じられる品
故人様が残した直筆の手紙や写真は、一度処分してしまえばもう二度と手にできない品です。一時の感情と判断に任せて処分せず、一時保管しておくことを強くおすすめします。
鍵
捨ててしまうと後々困ることも多いため。どこの鍵かわからない場合でも必ず残しておくようにしましょう。鍵屋に持っていけばどこの鍵か鑑定してもらえることもあるので、気になる場合は検討してみてはいかがでしょうか。
上記に当てはまらない場合や、穴が開いた衣服や古雑誌などあからさまな不用品でない場合は片付けを行っている方の独断で処分もしくは隠したり持ち出したりするのは厳禁です。品物の行方は相続人同士で話し合って決める必要があるからです。
また、仕分けを進める際には保管用の容器を用意したり、すでに片付けが終わっている部屋を一時的な保管場所にしておいたりするなどの工夫も大切です。
遺品整理中に残しておくべき品物リスト

分類のポイントをご紹介しましたが、ここでは具体的に残しておくべき品物をポイントごとにリスト化します。
相続関連品
・契約書
・権利書
・貴金属
・現金・通帳
相続に関連する品は行政手続きや、後々の相続に関する相談に使う大切な品です。
無用な混乱や親戚間での諍いを防ぐために、発見した品はできるだけそのままの状態で残しておくことも大切です。
捨ててはいけない品
・レンタル品
・免許証などの身分証
・クレジットカード
ここでの「捨ててはいけない」は正確に言うなら「所定の手続きを踏まないと処分してはいけない」という意味です。返却する必要がある品や、使わなくても年会費が発生するクレジットカードなど解約が必要になる品が該当します。
価値ある品
・貴金属・宝石・ジュエリー
・コレクション(切手・本・CD・DVDなど)
・家電類
・美術品
・万年筆・タイピンなどの高価な日用品
価値がある品は形見分けや売却品などに利用できます。
思い出の品
・写真
・手記(手紙・日記)
・故人が手掛けた作品
・衣服
・トロフィー・勲章・賞状
故人様との新しい思い出をこれから増やすことはできません。だからこそ思い出の残った品を大切にし、これからの人生を共に歩んでいく必要があるのです。思い出深い品に加え、故人様が残した功績を表す品や作品も残しておくといいでしょう。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
仕分けを行う際に注意すべきこと

仕分けを行う際には以下の4点に注意して進めていきましょう。
廃棄手段を考えておく
再利用は難しい型落ちした家電や日用品などは不用品として処分する必要があります。しかし、ただゴミとして出す場合には分別が必要なことに加え、一度に大量のゴミを出すと「一時多量ゴミ」扱いとなって回収を断られるケースも考えられます。
賃貸の場合なら退去日、遠方から片付けに来ている場合には帰らなければいけない日程などタイムリミットから逆算してゴミ出しを計画的に行うことと、間に合わない場合は利用する回収サービスを検討しておくことをおすすめします。
搬出方法を考えておく
廃棄手段と共通しますが、保管・処分に関わらず仕分けした品をどのように搬出・運搬するかも考えておく必要があります。運搬手段の確保・搬出ルートの確認・迷惑を掛けずに積み込みが行える駐車場所など考えておくべきことは多いです。
ライフライン停止のタイミングに注意
故人様が一人暮らしをされていた場合は節約のために水道・ガスなどのライフラインを早めに停止しようと考えられる方も多いかもしれませんが、最低でも遺品の仕分けが終わるまではライフライン停止は待ったほうが無難です。埃を被っている品物を洗浄したり、拭き掃除をしたりと作業に水を求められることは案外多いからです。
形見分け品の注意点
仕分け後に行われる形見分けは故人様の思い出がこもった品を親しかった方へと贈る行為です。だからこそできるだけ多くの方に贈りたいと思うものですが、品種によっては贈られても置き場に困るケースも考えられますので、実用性が高い品を贈ることや欲しい物を指定してもらうようにするなど、受け取る側の気持ちを慮ることも大切です。
遺品整理は業者へ依頼するのもおすすめ

ここまでは親戚・家族を含めて自力で遺品整理を進める方法をご紹介してきましたが、どうしても作業が困難だと感じた場合は専門の遺品整理業者に依頼するのもおすすめです。こちらの要望に合わせて適切に仕分け、他の品に紛れ込んでいた貴重品を探索してくれるなど遺品整理時に躓きやすいポイントをまとめて解決してもらえることは、初めて遺品整理を行うご家庭にとって非常に大きいメリットであるといえます。
その他にも業者に依頼するメリットは三つあり、一つは「作業時間を大幅に短縮できること」、二つ目に「処分も任せられること」、最後に「経験豊富なプロに任せられること」が挙げられます。特に三つ目は遺品整理時に陥りやすい「何から手を付けていいか分からない」→「迷っている間に作業時間が確保できなくなる」→「大切な品を誤って捨ててしまったり、きちんと供養ができないことで後悔が残る」という負のスパイラルから抜け出せることで納得のいく遺品整理が行えます。
まとめ
大切な方が残された遺品はどれも大切な物に思えるものですが、適切な整理を行わずにいつまでもそのままにしておくわけにもいかないもの。用途に合わせて適切に仕分け、本当に必要な物だけを残すことは大切な思い出を選び取り、これからの人生に持っていくことでもあります。故人様のため、引いては自分自身のためにも遺品整理は丁寧に行いたいものですね。