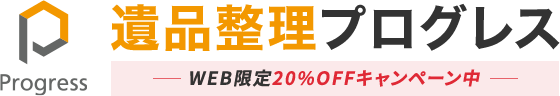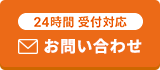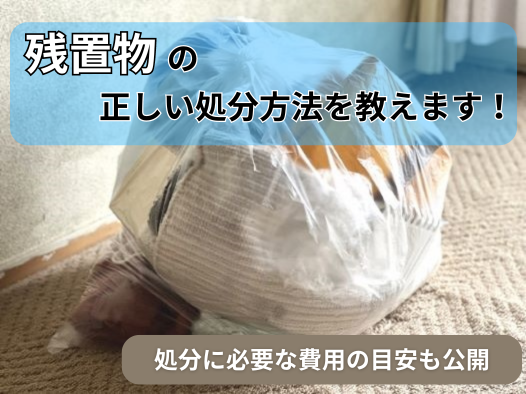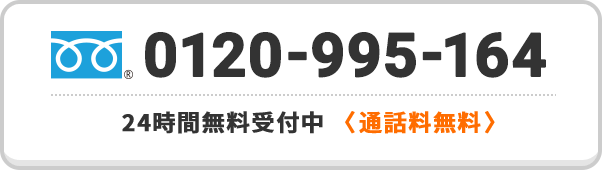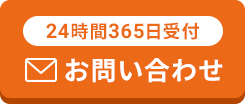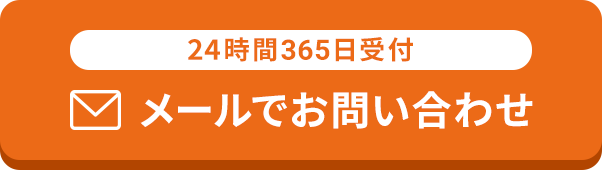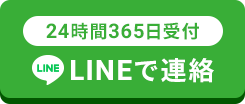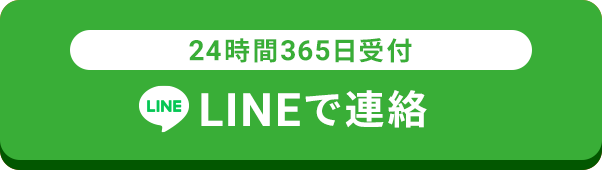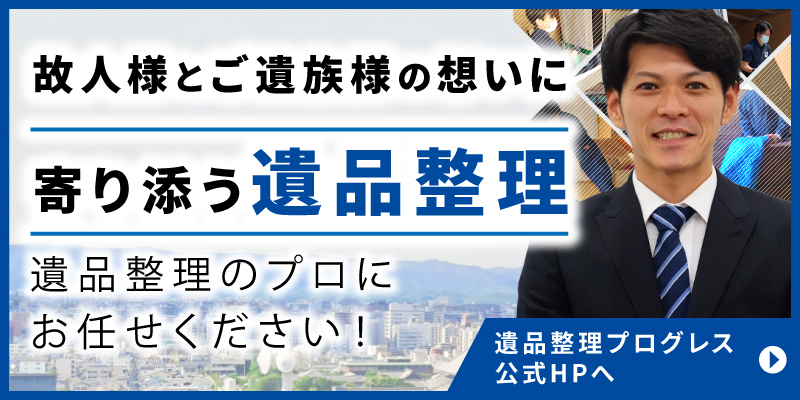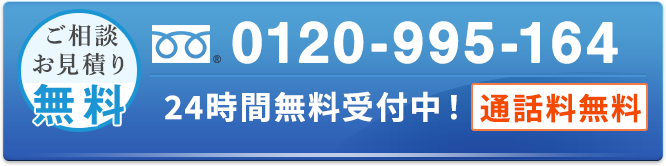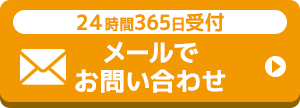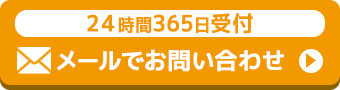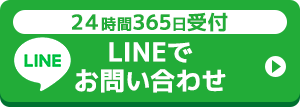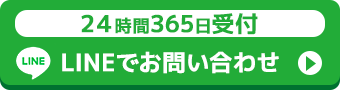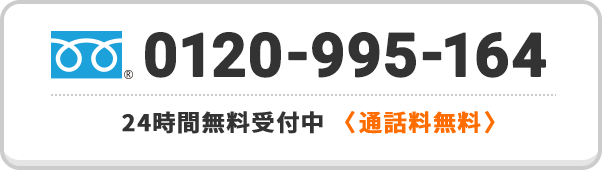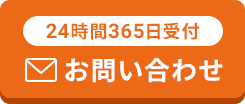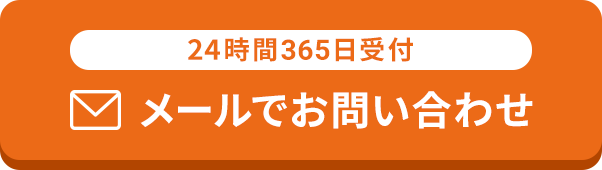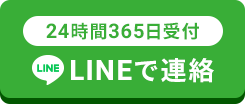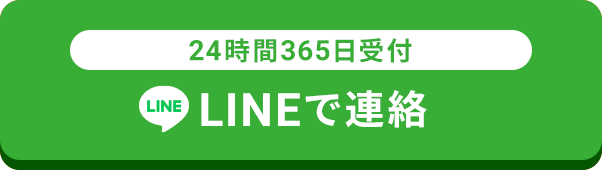賃貸物件では、退去後に残された残置物の適切な処分方法が問題になりがちです。
他人の物を勝手に処分すると、後でトラブルになるのではと心配になりますよね。
しかし、正しい処分方法に従って残置物を捨てれば、法律違反を避けられます。
まずは処分ルールについて理解することが重要です。
正しい処分方法を知っておくことで、残置物の処分に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
残置物を正しく処分し、スムーズに次の借主を迎えられるよう、処分方法をしっかりと学びましょう。
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
残置物の定義を解説!入居者の許可がなければ無断で処分できない

賃貸物件に住んでいた方が引越し、夜逃げ、突然死などで残した日用品や家具、家電などは残置物となります。
残置物と一般ゴミの違いは所有権の有無にあります。
前の入居者に所有権がある物は残置物、所有権を手放している物は一般ゴミとして扱います。
そのため、所有権を手放していない物は、一般ゴミとして勝手に処分できません。
残置物の代表例には、クーラーや洗濯機が挙げられます。
取り外しの手間や費用を惜しみ、次の人が使うだろうとそのままにして退去するケースが多いのです。
生活ゴミだけでなく、大型家具や家電など一般ゴミとして出せない物も残置物に含まれます。
残置物を撤去する場合、費用は一旦賃貸物件のオーナーが負担しますが、後から入居者や相続人に請求します。
店舗や事務所などの残置物には、机や椅子、棚などの家具、暖房・消火設備、オフィス機器などが含まれます。
さらに、原状回復工事が行われていない場合、厨房カウンターやオフィスの仕切りも残置物として放置されることがあります。
マンションなどの賃貸物件でも同様に、前入居者がオーナーに譲渡していれば、設備の一部として利用できます。
こうしたルールを理解し、残置物の適切な処理を心がけましょう。
高齢者の孤独死によって発生した残置物の処理が社会問題に
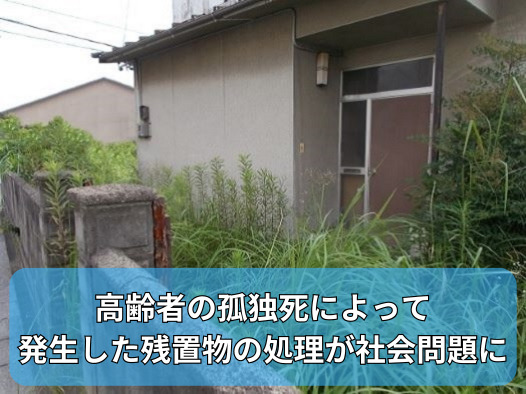
近年、単身で賃貸物件に入居していた高齢者が孤独死し、片付ける人が現れないまま残置物が部屋に放置される問題が増加しています。
単身入居者が亡くなると、賃借権と残置物の所有権は相続人に継承されますが、相続人が見つからない場合は、家主が残置物を撤去しなければなりません。
しかし、その撤去にも相続人や身元引受人の合意を得るために様々な手続きが必要です。
その結果、残置物を処分できないまま放置し、次の借主と契約を結べない問題が発生しています。
こうした残置物の処理問題を回避するため、一部の家主は高齢の単身者の入居を断ることもあります。
この問題に対処するため、国土交通省は高齢の単身者が住居を確保できるよう、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。
これにより、入居者の死亡時における残置物の廃棄を、相続人や管理会社に委託できるようになりました。
*参考サイト
【【家主さん向け】60歳以上の単身入居者の死亡時、簡便な方法で残置物を処分する方法を取りまとめたガイドブック」国土交通省】
残置物を勝手に処分するのは違法!合意を得てから処分を
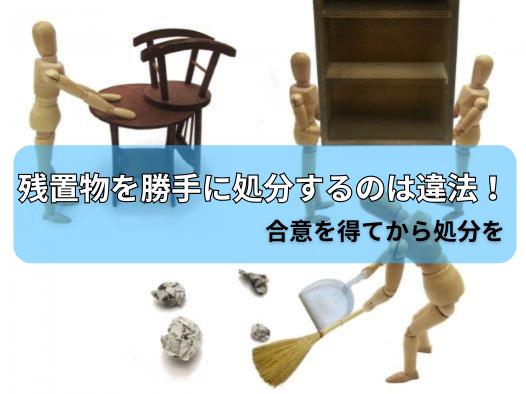
家主や新しい部屋の借主が残置物を処分するには、相続人との話し合いで合意を得なければいけません。
神奈川弁護士会のホームページに掲載されている「こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~」によれば、入居者の残置物を勝手に処分すると、民事上は無断で荷物を毀損したと損害賠償請求を受けり可能性があり、刑事上は器物損壊罪等に問われる可能性があるとされています。
*参考サイト
【こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~】神奈川県弁護士会
では、残置物は合意を得ないかぎり処分できないのでしょうか。
残置物を合法的に処分するには、弁護士へ依頼して裁判所に訴訟を起こし、強制的に処分を執行する許可を得る必要があります。
しかし、弁護士への依頼には高額な費用がかかります。
できるだけ保証人や相続人に連絡を取り、撤去してもらうのが望ましいでしょう。
適切な手続きと合意を得て、スムーズに残置物を処分するために、事前の準備と理解が大切です。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
残置物の処分に必要な費用の相場は?料金が大きく変わる理由は何?
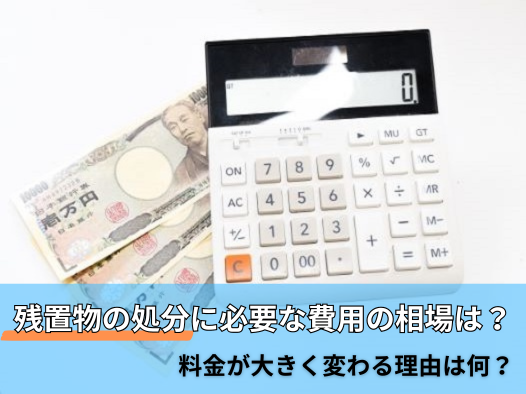
一人暮らし向けの1LDKや2DKの残置物を回収する場合、費用の相場は5~20万円です。
しかし、残置物の処分費用は、自身の手で処分するか業者に依頼するかで大きく変わります。
自分で行う場合、自治体の収集を利用すれば最安で無料、またはゴミ袋代程度に抑えられます。
ただし、残置物にはリサイクル料金がかかる大型ゴミや家電が含まれていることが多いため、必ずしも費用を抑えて処分できるとは限りません。
業者に依頼する場合、残置物の費用は1㎥あたりで判断されることがほとんどです。
1㎥と聞くと想像しづらいかもしれませんが、軽トラックに荷物を最大まで積むと2.5〜3㎥になるため、量の目安になるでしょう。
1㎥の処分費用の相場は、5,000円〜15万円程度と言われています。
さらに、ゴミの種類や量、エレベーターの有無などによって料金が変動するため、費用は大きく変わることがあります。
適切な方法を選び、予算に合わせて処分を行いましょう。
残置物の処分費用を抑えるために、自治体の無料回収を利用しましょう
残置物の処分費用を減らすためには、自治体の無料回収を徹底的に利用しましょう。
生活ゴミはもちろん、プラスチックやペットボトルなどの資源ゴミも無料で処分できます。
プラスチックや薄い金属で作られた家具は、自分で分解してゴミ袋に入れれば、処分費用を節約できます。
さらに、お住まいの地域にあるスーパーマーケットやホームセンターでは、古紙や衣類、小型家電の無料回収ボックスが設置されていることがあります。
筆者も、買い物のついでに最寄りのスーパーマーケットに設置された衣類の無料回収ボックスを利用しています。
回収ボックスに投函した物は資源として新しい製品に生まれ変わるため、ゴミとして処分するよりも罪悪感がなく、気持ちよく手放せます。
ただし、無料回収を利用する際は、住宅街を軽トラックで巡回している業者には引き取りを依頼しないようにしましょう。
「無料で回収いたします」と宣伝しいる業者の多くは、無許可で廃品を回収している可能性が高く、法外な料金を請求される恐れがあります。
大量の残置物を素早くお得に処分する方法をご紹介
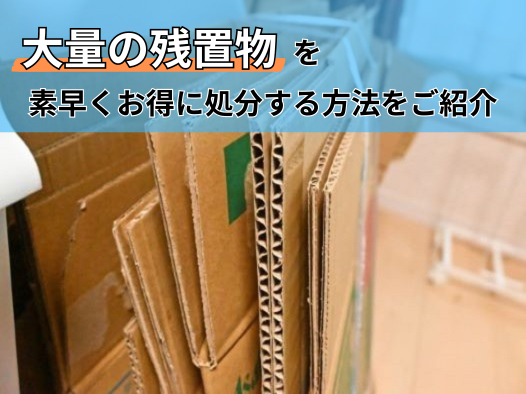
大量の残置物は、リサイクルショップへ買取を申し込んだり、地域のゴミ処理センターへ持ち込んだり、遺品整理業者に依頼して処分します。
需要が高い物、状態が良い物はリサイクルショップで売却する
希少性が高い物や良好な状態の物であれば、リサイクルショップで売却できます。
人気のブランドや使用感が少ない物でなければ、高額な買取価格は期待できないかもしれませんが、全体の処分費用を抑えられます。
筆者が遺品整理をしたときは、まず不要な物をリサイクルショップに持ち込み、値段がつかなかった物はゴミとして処分しました。
買取金が得られるだけでなく、ゴミの削減やリサイクルにも貢献できるため、積極的に利用しています。
お店まで運べない残置物があれば、出張買取サービスを申し込めば査定してもらえます。
お店へ持ち込む手間や査定にかかる時間を考慮し、急ぎでない残置物を処分したい場合は、一度買取査定を依頼するのがおすすめです。
ゴミ処理センターで受け入れ可能な品目を確認し、持ち込んで処分する
車に残置物を積み込み、お住まいの近くにある処理センターまで搬入して引き取ってもらう方法です。
ゴミをまとめて持ち込めば、粗大ゴミを一点ずつ回収してもらうよりも費用を抑えられます。
処理センターによっては予約が必要な場合もありますので、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
ただし、テレビや冷蔵庫、エアコンなどの家電リサイクル法対象品は、粗大ゴミとして処理センターで引き取ってもらえません。
これらの家電は自治体指定の店舗や家電量販店にリサイクル料金を支払って回収してもらう必要がありますので、誤って処理センターに持ち込まないように注意しましょう。
急いで大量の残置物を片付けたい場合は遺品整理業者を利用する
遺品が大量にあり、片付けが困難な場合や、マンションやアパートの退去日が迫っている場合は、遺品整理業者の利用がおすすめです。
残置物は通常、直前まで使用していた状態で放置されているため、引越し時と同様の量の家具や日用品を処分しなければいけません。
小さな燃えるゴミやペットボトルなどは一般ゴミとして処分できますが、家具や家電などの粗大ゴミは指定された日時に回収場所に出す必要があります。
遺品整理業者に依頼すると、残置物を分別してもらえるだけでなく、重たい物も代わりに搬出してもらえます。
回収された残置物は、福祉施設や海外に寄付されたり、処理場で適切に処理されます。
遺品整理士が在籍している遺品整理業者を利用すれば、相続品の発見や解約手続きについてアドバイスを受けることもできます。
人手が足りない場合や、時間をかけて処理したくない方には、ぜひ遺品整理業者の利用を検討してみてください。
まとめ
残置物は、必要のなさそうな物であっても独断で処分することができず、非常に扱いに困ります。
室内にいつまでも残置物を放置しておくと、不要な家賃支払いを続けなければいけません。
さらに残置物の劣化が進めば、害虫や悪臭が発生しやすくなります。
残置物を処分する際は、前の入居者や保証人に連絡して許可を得るよう心がけましょう。
法的なルールに従って残置物を処分することで、トラブルを未然に防げます。