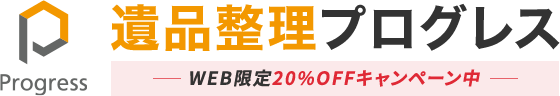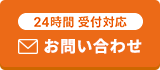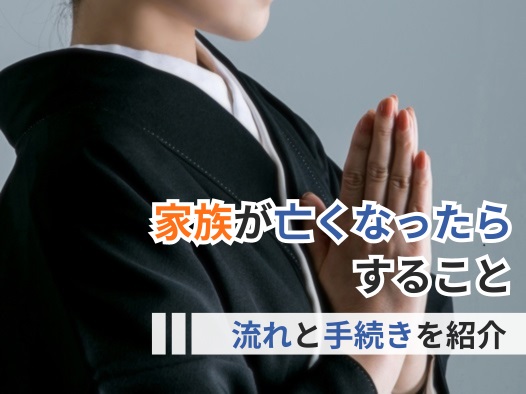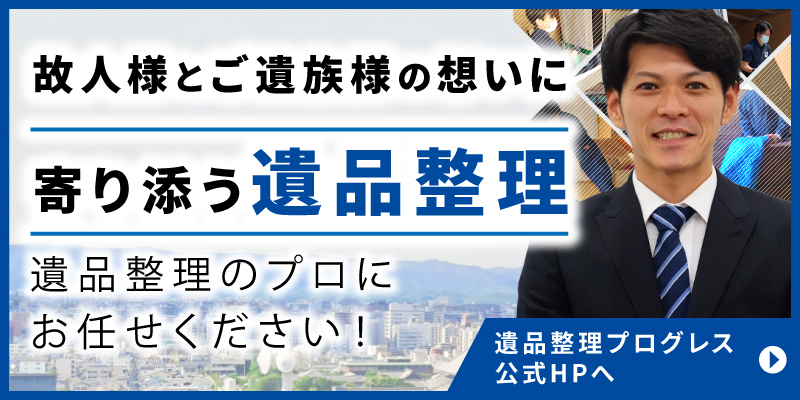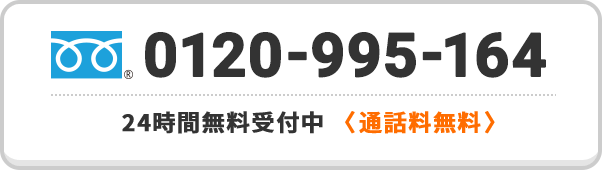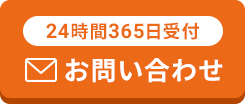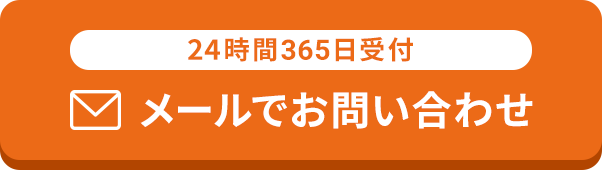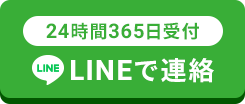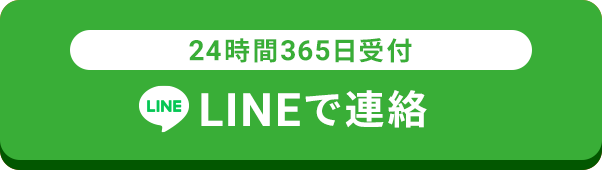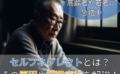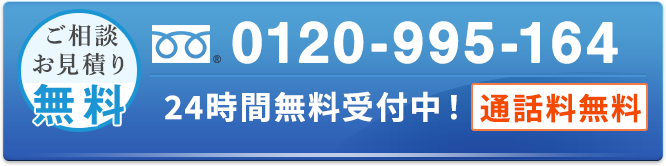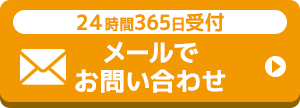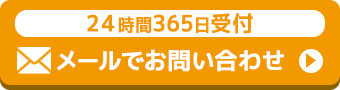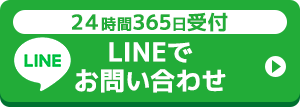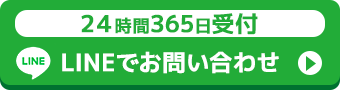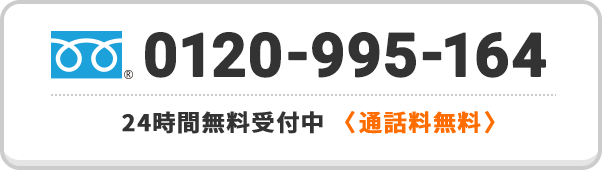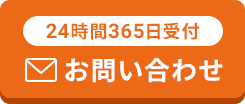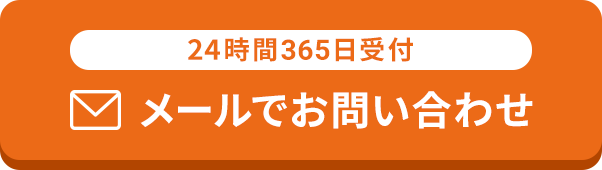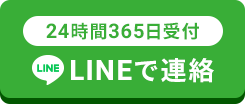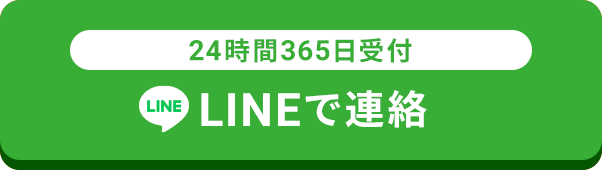親や家族が亡くなることは、誰にとっても深い悲しみを伴います。
その後には、様々な手続きや準備が必要です。
筆者も家族を亡くした際、期限内に手続きを進めることが多く、大変な思いをしました。
ほとんどの方がそうだと思いますが、初めて経験することが多いため、何から手をつけるべきかわからず、困惑することも多いでしょう。
そこで、この記事では、親や家族が亡くなった際に必要な手続きを、時系列で詳しくご紹介します。
必要な手続きから葬儀、遺品整理まで、わかりやすく解説していますので、ご家族と一緒に確認したり、周囲で困っている方にも教えてあげたりする際に役立ててください。
この記事は、次のような方におすすめです
・家族や身内の突然の死に直面している方
・亡くなった後に必要な手続きや準備について知りたい方
・手続きの期限や具体的な情報を求めている方
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
家族が亡くなった直後にすること

医師に死亡確認をしてもらう(死亡診断書の受け取り)
家族や身内が亡くなった場合、まず医師による死亡確認が必要です。
病院で亡くなった場合は、その場で医師が確認します。
一方、自宅で亡くなった場合は、救急車を呼び、医師による確認を受ける必要があります。
事故死や突然死(孤独死も含む)、自殺などの場合は、警察に連絡し、警察医や監察医が検案と身元確認を行います。
①病院で亡くなった場合
主治医や臨終に立ち会った医師が死亡診断書を作成してくれます。
この診断書には、死因や医学的事実が可能な限り詳しく記入されます。
死亡診断書の発行にあたって、家族が特別に行う手続きはありません。
医師が手続きを進め、通常は当日中に発行されます。
②家で亡くなった場合
故人が生前に病気で通院していた場合、かかりつけ医に死亡診断書の作成を依頼します。
医師が診察を行い、通常は当日中に死亡診断書を発行してくれます。
ただし、持病や老衰以外の原因で死亡した場合は、検視が必要です。
この場合、24時間以内に警察に連絡する必要があります。
③事故死、突然死(孤独死なども含む)、自殺で亡くなった場合
突発性の発作や事故、自殺などで亡くなった場合、または別居している親が孤独死などで亡くなった場合は、まず警察に連絡します。
警察による検視・検案の後、死因がすぐに判明すれば、検察医が死体検案書を作成し、遺族に渡します。
死因が明らかになった場合、通常1日から数日で検案書を受け取ることができ、遺体も家族の元へ返されます。
発行はいつ?
死亡診断書:一般的に死亡当日か翌日
死体検案書:死因がすぐに判明した場合、通常1日から数日以内
死亡診断書・死体検案書は、今後の手続きで必要になるため、次章で紹介する死亡届と一緒にコピーを複数枚とっておきましょう。
遺体を搬送する
病院で亡くなった場合、半日程度で遺体を搬送する必要があります。
葬儀社の安置室や自宅への搬送を検討しましょう。
この際に重要なのは、故人が葬儀について希望を残していなかったかを確認することです。
遺言書やエンディングノートに記載されている場合もあるので、故人の意思を尊重しながら、適切な葬儀社を選びます。
ただし、すぐに決められない場合は、まず搬送だけを依頼できる葬儀社を探すのが良いでしょう。
また、搬送と同時に入院費の精算などの退院手続きも行うため、必要な費用を準備しておくのを忘れないようにしましょう。
葬儀社を選ぶ
葬儀の内容や日程を葬儀社と話し合い、手配を進めます。
死亡診断書があれば、死亡届の提出や埋火葬許可証の発行も葬儀社に依頼できます。
葬儀社選びのポイントは以下の通りです。
・葬儀ブランの種類
(一般葬、家族葬、一日葬、直葬など)
・価格
・オプションの豊富さ
(祭花壇、遺体の搬送、遺体の安置、死亡届の提出、埋火葬、法要など)
信頼できる葬儀社を選ぶために、疑問点を明確にし、見積書の内容に納得してから契約しましょう。
そのためには、複数の葬儀社を比較検討し、予算や希望に合ったところを選ぶことが大切ですが、時間的な余裕がない場合もあるでしょう。
病院で亡くなった場合、特に希望がなければ、その病院が提携している葬儀社を利用する方法もあります。
自宅で病気により亡くなった場合は、かかりつけ医や近所の人に相談するか、地域の葬儀社に連絡してみましょう。
親族や友人に訃報を連絡する
遺体の安置場所が決まったら、親族や親しい友人に訃報を連絡します。
故人の関係者へは、できるだけ当日中に連絡し、通夜や葬儀の日程が決まっている場合は一緒に伝えましょう。
連絡の優先順位としては、家族や親戚が最優先となります。
事前に連絡リストを準備しておくと、スムーズに対応できます。
親や家族が亡くなったら仕事を何日休むことができるのでしょうか?
親が亡くなったときの忌引き休暇は、一般的には7日間とされています。
配偶者が亡くなった場合は10日間、祖父母や兄弟姉妹、義理の父母の場合は3日間の休暇を取ることが一般的です。
ただし、会社によって規定が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
死亡届の提出と埋火葬許可証の受け取り
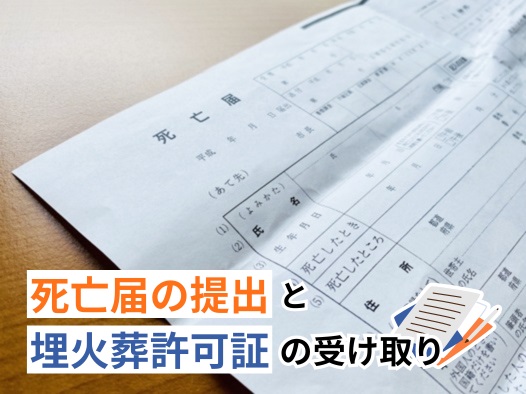
亡くなったことを役所に届けるためには、まず死亡届を提出する必要があります。
この届が受理されると、埋火葬許可証が発行されます。
この許可証がなければ、埋火葬を行うことはできず、葬儀も進められません。
そのため、葬儀を行うためには、死亡届の提出と埋火葬許可証の受け取りが不可欠です。
死亡届は、死亡診断書や死体検案書と一体になっており、用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書および死体検案書です。
以下の手順で提出します。
死亡届の提出の仕方
①必要事項を記入する
・故人が亡くなった場所
・本人の本籍地
・届出人の居住地
・捺印
②提出先
・故人の死亡地の市区町村役場
・故人の本籍地の市区町村役場
・届出人の住所地の市区町村役場
いずれか一個所に提出すれば、手続きが完了します。
③注意点
・提出期限は、死亡を知った日から7日以内
・今後の手続きで必要になることが多いため、死亡届の原本を提出する前にコピーを複数枚とっておく
死亡届は、前章で紹介した死亡診断書(死体検案書)と一体になっていますので、記入後に一緒にコピーしておきましょう。
埋火葬許可証の受け取り
死亡届が役所に受理されると、火葬場での火葬を許可する「埋火葬許可証」が発行されます。
①火葬許可証の重要性
・許可証がなければ火葬できない
・火葬は、法律によって死亡後24時間が経過してから行うことが義務付けられている
②提出先
火葬場に提出する(多くの場合、葬儀社が代行してくれます)
葬儀を円滑に進めるため、通常は、葬儀社が死亡届の提出と、埋火葬許可証の受け取り手続きを代行してくれます。
葬儀の打ち合わせのときに必ず確認しておきましょう。
葬儀を執り行う

葬儀社との打ち合わせ
葬儀社を選んだ後、具体的な打ち合わせを行います。
通常、葬儀には以下の儀式が含まれます。
・通夜
・お葬式
・告別式
・火葬
この際、形式や日程、場所、参列者の役割分担などを相談して決定します。
近年では、親族の都合や故人の希望に応じた様々な形式の葬儀が増えています。
遺族の意向を尊重し、十分に相談を重ねることが大切です。
通夜
通夜では、僧侶による読経や参列者の焼香が行われ、慰問客には通夜の膳が提供されます。
伝統的には、遺体を見守る「寝ずの番」が行われていましたが、現在では「半通夜」が一般的です。
葬儀社が会場の準備を整えることが多いですが、宗派や地域によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
お葬式と初七日
葬儀社が打ち合わせ通りに進め、故人との最後の別れを行います。
お葬式が終われば火葬場に向かい、そこで読経と焼香が行われます。
その後、親族で骨上げを行い、葬儀は終了します。
初七日は、亡くなってから7日目の法要ですが、現在では葬儀後に直接行うことが多くなっています。
四十九日
仏教では、故人の成仏を願い、冥福を祈る儀式を「法要」と呼びます。
中でも四十九日の法要は特に重要で、故人の魂が浄土へと旅立つ節目とされています。
通常は遺族のみで行われますが、僧侶を招き、親族や友人も参列する大規模な法要にすることもあります。
これが一般的な葬儀の流れですが、家族葬や直葬など、現代のライフスタイルに合わせた形式も増えてきています。
葬儀の費用と香典について
葬儀の費用については法律で特に定められておらず、一般的には喪主が負担します。
香典は喪主のものとされ、通常は葬儀費用に充てられます。
お骨はお墓に納めるのが一般的ですが、お墓が準備されていない場合、一時的に自宅で保管することも可能です。
管理が難しい場合は、お寺や霊園による「永代供養」を検討するのも一つの方法です。
このように、葬儀に関する手続きや準備は、丁寧に打ち合わせを重ねながら進めることが重要です。
葬儀後に行う手続き

亡くなったあと、葬儀を経て四十九日までにすべきことはたくさんあります。
様々な手続きが必要になりますが、それぞれに期限が設けられていますので、忘れずに行いましょう。
年金の受給停止手続き
亡くなった方の年金受給を停止するため、年金事務所に連絡しましょう。
【申請先】
年金事務所
年金相談センター
【必要書類】
・年金受給権者死亡届(報告書)
・年金証書
・死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
【提出期限】
厚生年金の場合:死亡後10日以内
国民年金の場合:死亡後14日以内
*参考サイト:日本年金機構『年金を受けている方が亡くなったとき』
健康保険の資格喪失届の提出(14日以内)
【国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合】
申請先:市区町村の役所
提出期限:死亡後14日以内
【健康保険の場合】
申請先:年金事務所(多くの場合、会社が退職手続きと併せて行います)
提出期限:死亡後5日以内
介護保険の資格喪失届の提出(14日以内)
亡くなった方が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失届を提出します。
【申請先】
市区町村の役所
【必要書類】
・介護保険証
・介護保険資格喪失届
【提出期限】
死亡後14日以内
住民票の世帯主変更届の提出(14日以内)
亡くなった方が世帯主だった場合、同居人を新たに世帯主に変更するための「世帯主変更届」を提出しなければなりません。
【申請先】
市区町村の役所
【期限】
死亡後14日以内
*正当な理由なく提出しなかった場合、5万円以下の過料が課せられます
雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
亡くなった方が雇用保険を受給していた場合、受給資格者証の返還が必要です。
【申請先】
雇用保険を受給していたハローワーク
【提出期限】
死亡後1カ月以内
国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
死亡一時金は国民年金の第1号被保険者として、国民年金保険料を一定期間以上納めていた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡した場合、遺族に支給されます。
*遺族基礎年金を受け取る場合は、死亡一時金は支給されません
【申請先】
市区町村の役所、年金事務所、年金センター
【必要書類】
・亡くなった方の基礎年金番号がわかる書類
・亡くなった方の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
・亡くなった方の住民票の除票
・世帯全員の住民票の写し
・受取先金融機関の通帳など
【申請期限】
死亡日の翌日から2年以内
参考サイト:日本年金機構『死亡一時金を受けるとき』
埋葬料請求(2年以内)
亡くなった方が健康保険の被保険者の場合は、「埋葬料」として5万円を請求できます。
【申請先】
亡くなった方が加入していた健康保険組合または協会けんぽ
【必要書類】
・健康保険埋葬料支給請求書
・亡くなった方の健康保険証
・死亡診断書、埋火葬許可証など
・葬儀費用の領収証など
【申請期限】
死亡日の翌日から2年以内
葬祭費の請求(2年以内)
亡くなった方が国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた場合、その遺族は市区町村の役所に「葬祭費」を請求できます。
葬祭費は一般的に1万円から7万円の範囲で、具体的な金額はご家族の状況や市区町村の方針によって異なります。
【申請先】
亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
【必要書類】
・亡くなった方の健康保険証
・死亡の事実が確認できるもの(埋火葬許可証など)
・葬祭費用の領収証
・申請者の本人確認書類
・誓約書
など
【申請期限】
葬祭を行った日の翌日から2年以内
高額医療費の還付申請(2年以内)
入院などで高額な医療費が発生した場合、その一部を健康保険から還付してもらうことができます。
【申請先】
亡くなった方が加入していた健康保険組合、協会けんぽ(共済組合員共済組合)、市区町村の役所
【必要書類】
医療費の明細書
【申請期限】
医療費の支払いから2年以内
遺族年金の請求(5年以内)
配偶者が亡くなった場合、遺族は「遺族年金」を受給する資格があります。
この場合、年金事務所に遺族年金の申請を行わなければなりません。
申請を怠ると、遺族年金が支給されない可能性がありますので、早めに手続きをすることが重要です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類があり、どちらが支給されるかは家族の構成や収入などによって異なります。
例えば、亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者には、「遺族基礎年金」が支給されます。
この基礎年金額は、年間で79万5000円に子供の加算額が加えられます。
子供が18歳に達する年度末まで受け取ることができるため、家計を支える大きな支援となります。
【申請先】
年金事務所
【必要書類】
・年金手帳(故人および請求者のもの)
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・亡くなった方の住民票の除票
・請求者の収入証明書
・子どもの収入証明書
・死亡診断書のコピー
・受取先金融機関の通帳
・印鑑
【請求期限】
死亡後5年以内
故人の未支給年金の請求(5年以内)
年金は毎月支給される制度であり、通常は前月分の2カ月分が翌月に支払われます。
しかし、年金受給者が亡くなると、その時点で未払いの年金が発生します。
この未払いの期間分の年金を「未支給年金」と呼びます。
遺族は、亡くなった方が受け取るはずだった未払いの年金を請求することができます。
【申請先】
年金事務所
【必要書類】
未支給年金請求書
【申請期限】
死亡後5年以内
これらの手続きは、それぞれの期限内に正確に行うことが重要です。
具体的な手続きや必要書類については、役所や関連機関に直接確認することをおすすめします。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
税金関係の手続き

親や家族が亡くなった場合、以下の税金関係の手続きが必要になります。
・所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)
・固定資産税の納税・現所有者申告
・相続税の申告・納税(10カ月以内)
これらの手続きは期限を守ることが重要です。
申告期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)
亡くなった方が事業者であった場合や、年収が2000万円を超える給与所得者だった場合など、本来確定申告を行うべき状況にあった場合、その申告を相続人が代わって行うことを「準確定申告」と呼びます。
特に、ご家族が個人事業主であった場合にはこの手続きが必要です。
所得税の準確定申告とは、亡くなった方の事業や収入に関する確定申告を相続人が行うことです。
【提出先】
故人の住所地を管轄する税務署
【申告期限】
死亡を知った日の翌日から4カ月以内
固定資産税の納税
年の途中で固定資産(家や建物など)の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人に引き継がれます。
具体的には、亡くなった時点から年末までの期間について相続人が納税を行います。
【支払先】
固定資産がある市町村
相続税の申告・納税(10カ月以内)
遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合に、相続税の申告と納税が必要です。
基礎控除は「3000万円+法定相続人数×600万円」です。
【提出先】
亡くなった方の住所地を管轄する税務署
【申告期限】
死亡を知った日の翌日から10カ月以内
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった控除、特例制度があります。
これらの特例は、相続税の申告をしないと適用されないため、相続税額がゼロであっても、必ず申告を行わなければなりません。
こうした控除や特例制度は、適用を受けるための要件が複雑で、多くの申告書類を準備する必要があります。
相続税の申告・納税について不安がある場合は、税理士に相談しましょう。
相続税の手続きは、早めに準備を始めることが重要です。
期限を守って正確に申告を行うことで、延滞税や無申告加算税などの不要なペナルティを回避し、税金の負担を最小限に抑えることができます。
*遺品姓整理中にお金が出てきた場合の相続税は?*
こちらの記事で疑問にお答えしています!
遺産相続に関する手続き
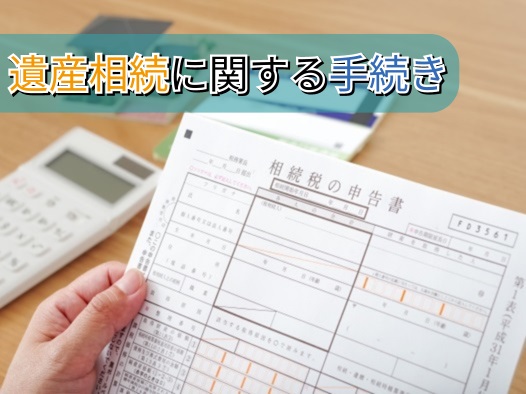
遺産相続に関する手続きは、以下の通りです。
・相続人調査
・相続財産調査
・遺言書を探す
・遺言書の検認
・相続放棄、限定承認の検討と手続き(3カ月以内)
・遺産分割
・相続税の計算、申告・納付
・相続登記(不動産の名義変更)(3年以内)
・銀行の預貯金払い戻し、名義変更
・株式の名義変更
・自動車の売却、名義変更、処分(廃車)
相続人調査
①相続人調査の開始時期
家族が亡くなったら、早めに相続人調査を始めましょう。
これには被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集める必要があります。
②戸籍謄本の取得
2024年3月からは、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本類を取得できるようになりました。
ただし、兄弟姉妹の戸籍類やコンピューター化されていない戸籍類、戸籍の附票は本籍地の役所に直接申請して発行してもらいます。
③申請先と必要書類
【申請先】
申請者の最寄りの役所(一部本籍地を管轄する役所)
【必要書類】
・申請書
・申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真入り)
【本籍地の情報】
申請に際しては取り寄せの手がかりとなる本籍地の情報が必要です。
最後の本籍地がわからない場合は、被相続人の最後の住所地で「住民票の除票」を本籍地の記載入りで取得して調査に役立てます。
相続人調査は、正確な相続手続きを行うために欠かせないステップです。
手続きをスムーズに進めるためにも、早めに必要な情報を集めておくことが重要です。
相続財産調査
相続財産調査の目的は、被相続人が残したすべての財産を特定し、その価値や内容を明らかにすることです。
これにより、遺産分割や相続税の計算に必要な情報を得ることができます。
①実施方法
· 自宅内での調査
まず、被相続人の自宅内で遺品を探し、通帳や資料などを集めます。これにより銀行口座やその他の財産に関する情報を入手します。
· 金融機関への問い合わせ
被相続人が口座を持っていた金融機関に対して、「残高証明書」や取引履歴などを求めて調査します。これにより、預貯金や投資資産などの詳細な情報を入手します。
· 証券会社からの情報取得
被相続人が証券取引をしていた場合、関連する証券会社に問い合わせをし、口座残高や保有株式などの情報を調査します。
· 法務局からの不動産情報取得
被相続人が不動産を所有していた場合、法務局から「不動産の全部事項証明書」を取得して、その所有状況や評価額などを確認します。
②手続きのポイント
調査の際には、遺産に関するすべての情報を正確に収集し、相続人間で共有することが重要です。
また、遺言書がある場合にはその内容に基づいて遺産を分割するため、調査結果は後の手続きに影響します。
相続財産調査は、細部にわたる情報収集が必要となりますが、正確な調査を行うことでスムーズな相続手続きを進めることができます。
遺言書を探す
遺言書が残されていないか確認しましょう。
自宅の机、棚、タンス、引き出しなど、被相続人の普段使いの場所に遺言書が保管されていることが多いです。
もし被相続人が貸金庫を利用していた場合は、貸金庫に遺言書が保管されている可能性があるので、早めに相続人が集まって貸金庫の中身を確認しに行きましょう。
公正証書遺言が存在している場合、公証役場に行けば遺言書を検索してもらえます。
遺言書が見つかれば、基本的にその遺言書に従って遺産を分割することになります。
遺言書がある場合は遺言書に従って遺産を分けるため、後述する遺産分割協議は必要ありません。
遺言執行者が指定されていればその人が手続きを進めます。
遺言書の探索は、相続手続きにおいて重要な初期段階です。
遺言書が見つからない場合でも、公証役場や他の関連機関での確認を怠らず、適切に手続きを進めることが大切です。
遺言書の検認
遺言書が見つかったら、すぐに家庭裁判所で遺言書の「検認」の申し立てをしましょう。
遺言書を発見した場合、その遺言書の内容が正当であることを確認する手続きです。
検認を受けないまま遺言書を開封すると、法律により最大5万円以下の過料が科される可能性があります。
遺言書は勝手に開封してはいけません。
これは、遺言書の偽造や変造を防止するためです。
遺言書は開封前に「検認」という手続きを受けることが義務付けられています。
【検認の申請場所】
被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所
【必要書類】
・遺言書
・遺言者の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
・相続人全員の戸籍謄本(相続人によっては、他の戸籍謄本類も必要になる場合がある)
・費用(検認手続きには、収入印紙800円と郵便切手代は必要)
検認が完了すると、遺言書の内容が法的に認められ、相続手続きが円滑に進むようになります。
遺言書がある場合とない場合の違い
【遺言書がある場合】
1.遺言の内容が優先される
遺言書に記載された通りに遺産が分配されます。
遺言書は法的に有効であれば、基本的に遺言者の意向が最優先されます。
2.遺産分割協議が不要
遺言書に従って遺産を分けるため、相続人間での協議は必要ありません。
3.遺言執行者の指定
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、その人が遺産の管理や分配を行います。
【遺言書がない場合】
1.法定相続分に従う
民法に定められた法定相続分に基づいて、相続人間で遺産が分配されます。
例えば、配偶者と子供が相続人であれば、それぞれに定められた割合で遺産が分けられます。
2.遺産分割協議が必要
相続人全員が参加する遺産分割協議を行い、全員の合意のもとで遺産を分配します。
合意が得られない場合は家庭裁判所に調停や審判を申立てることになります。
3.遺言執行者がいない
特定の遺言執行者がいないため、相続人全員で遺産の管理や分配を進める必要があります。
相続放棄、限定承認の検討と手続き(3カ月以内)
亡くなった方(被相続人)に多額の負債があった場合は、相続放棄しましょう。
相続放棄を行うと、資産も負債も一切相続しません。
限定承認とは、資産と負債を相殺した結果、プラスになる部分だけを相続する方法です。
ただし、限定認証の申述は相続人全員で行わなければならないなどのデメリットがあります。
【申請先】
被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所
【必要書類(相続放棄の場合)】
・相続放棄申述書
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の住民票除票
・申述人の戸籍謄本
など
※相続放棄の必要書類は、被相続人との続柄によって異なることがあります。
【申請期限】
被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内
遺産分割
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定する必要があります。
協議が終わったら、遺産分割協議書を作成します。
もし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行い、遺産の分け方を決定しなければなりません。
調停でも合意できない場合は、「遺産分割審判」となり、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。家族仲が普段から不仲だと、相続争いに発展する恐れがあります。
遺産分割で揉めて相続争いが発生しそうな場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士が交渉の代理を努め、円滑に解決へ導いてくれます。
相続税の計算、申告・納付
遺産の分け方が決まったあとは、相続税を計算し、10カ月以内に納める必要があります。
相続税額は、不動産や金融資産の評価額を正確に把握し、厳格なルールに従って計算します。
相続税を抑えるための特例の適用も検討しましょう。
計算ミスがあると、税務調査で指摘され、追徴課税を受ける可能性があります。
不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
相続登記(3年以内)
遺産分割協議や調停・審判で遺産分割の方法が決まったら、相続した不動産の名義変更(相続登記)を行います。
2024年4月から相続登記は義務化され、相続から3年以内に行わないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
【申請先】
不動産の管轄の法務局
【相続登記に必要な書類】
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産取得者の住民票
・固定資産課税明細書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒
相続には3つのケースがあります。
「遺産分割協議による相続」「法定相続分による相続」「遺言による相続」です。
それぞれのケースに応じて申請に必要な書類が異なりますので、上記の書類に加えて以下の書類が必要となります。
【遺産分割協議による相続】
遺産分割協議書
【法定相続分による相続】
法定相続分に従った相続関係説明図
【遺言による相続】遺言書
これらの追加書類を用意し、必要な手続きを行ってください。
*参考サイト:法務局『相続による所有者の登記の申請に必要な書類とその入手先等』
【申請期限】
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
不動産の名義変更手続きは司法書士が得意としていますので、代行を依頼することも検討しましょう。
銀行の預貯金払い戻し、名義変更
遺産に預貯金が含まれていた場合、銀行などの金融機関に連絡し、速やかに払い戻しや名義変更を行いましょう。
連絡すると、銀行口座は凍結され、名義変更が完了するまで預金の引き出しができなくなります。
【申請先】
取引先の金融機関
【必要書類】
・名義変更や払い戻しの申請書(金融機関が指定する様式)
・被相続人の預貯金通帳
・被相続人の銀行印または届出印
・被相続人のキャッシュカード
・被相続人の除籍謄本(または死亡届受理証明書)
・相続人全員の戸籍謄本(相続関係を証明するため)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印があるもの)
・遺言書(あれば)
詳細は取引先の金融機関に確認してください。
株式の名義変更
被相続人が株式取引を行っていた場合、その株式の名義変更を行う必要があります。
以下の手順と必要書類を確認してください。
【申請先】
証券会社
【必要書類】
・被相続人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・証券会社への届出印
・相続人の証券口座がわかる資料(証券会社の取引報告書など)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印があるもの)または遺言書
具体的な書類や手続きについては、取引先の証券会社に確認してください。
証券会社によっては追加の書類が必要になる場合があります。
自動車の売却、名義変更、処分(廃車)
遺産に自動車が含まれている場合、その自動車の名義変更や売却、廃車の処分手続きを行う必要があります。
【名義変更の申請先】
普通自動車:運輸支局
軽自動車:軽自動車検査協会
【必要書類】
・被相続人の除籍謄本
・相続人の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印があるもの)または遺言書
・車検証
・自動車税申告書
・車庫証明書(車の保管場所が変わる場合)
軽自動車の場合、軽自動車検査協会に名義変更の申請を行います。
また、名義変更だけでなく、自動車の売却や廃車の処分も考慮する必要があります。
処分方法については、遺産の状況や相続人の意向によって選択することができます。
具体的な手続きや書類については、地域や事情によって異なる場合がありますので、申請先の運輸支局や軽自動車検査協会に事前に確認してください。
その他の手続き

クレジットカードの利用停止
亡くなった方がクレジットカードを契約していた場合は、速やかに利用停止の手続きを行うことが必要です。
カードの裏面に記載された電話番号に連絡し、利用停止の手続きを依頼しましょう。
クレジットカード利用停止の手順
1.クレジットカード会社への連絡
クレジットカードの裏面に記載されている電話番号に連絡し、カードの利用停止を依頼します。
カード会社のカスタマーサポートが対応します。
連絡時には、故人の氏名、カード番号、死亡証明書の提出を求められる場合があります。
必要な情報や書類を手元に準備しておくとスムーズです。
2.必要書類の提出
・死亡証明書
・相続人の本人確認書類
・カード番号
3.カードの返却
利用停止の手続き後、カード会社からカードの返却を指示されることがあります。
指示に従い、カードを返却してください。
4.利用停止確認
カード会社から利用停止の確認通知が届く場合があります。
確認書類を受け取ったら、手続きが完了したことを確認します。
5.未払いの精算
クレジットカードに関連する未払いの残高がある場合、精算手続きを行います。
クレジットカード会社に連絡し、残高の確認と清算方法について指示を仰いでください。
運転免許証の返納
亡くなった方が所有していた運転免許証は、速やかに返納する必要があります。
【返納先】
自動車安全運転センターまたは警察署
【必要書類】
・亡くなった方の運転免許証
・死亡診断書の写し
・亡くなった方の除籍謄本
・提出者の身分証明書と印鑑
パスポートの失効手続き
亡くなった方が所有していたパスポートは、速やかに失効手続きを行いましょう。
【申請先】
パスポートセンター
【必要書類】
・亡くなった方のパスポート
・名義人が死亡したことがわかる書類(戸籍抄本、死亡診断書の写し、埋火葬許可証の写しのいずれか1つ)
・返納届(窓口にあり)申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
団体信用生命保険の請求手続き
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンなどを組んだ際に多くの人が加入しています。
この保険は、加入者が亡くなった場合に、保険金が支払われてローン残債を全額返済する制度です。
亡くなった方が団信に加入していた場合、金融機関に速やかに連絡し、保険金の請求手続きを行いましょう。
【申請期限】
一般的には死亡から数カ月から1年程度の間に手続きを完了する必要がある場合が多いですが、具体的な期限は契約内容によって異なりますので、契約書を参照するか、保険会社に直接問い合わせることをおすすめします。
生命保険金の受取り(3年以内)
亡くなった方が生命保険の被保険者だった場合、指定された受取人は保険金を受け取ることができます。
保険金を受け取るためには、早めに加入している生命保険会社に保険金の請求手続きを行う必要があります。
【請求先】
亡くなった方が加入していた生命保険会社
【必要書類】
・保険証書
・死亡診断書の写し
・亡くなった方の除籍謄本
・受取人の身分証明書
・印鑑
【請求期限】
死亡後3年以内
必要書類は、生命保険会社によって異なる場合があります。
詳細は加入している保険会社に確認しましょう。
電気、水道、ガスなどの公共料金の名義変更
亡くなった方が契約していた電気、水道、ガスなどの公共料金については、早急に名義変更手続きを行いましょう。
各公共サービス会社や市区町村に連絡すれば、手続きが可能です。
名義変更および解約手続きの手順
1.必要書類の準備
名義変更や解約手続きには、一般的に以下の書類が必要です。
・故人の死亡証明書
・相続人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・契約番号や契約者名がわかる書類
2.公共サービス会社への連絡
各公共サービス会社(電気、ガス、水道など)に連絡し、名義変更または解約の手続きを依頼します。
連絡方法としては、電話、メール、またはオンライン手続きが可能な場合があります。
●電気
各電力会社(東京電力、関西電力など)に連絡し、名義変更または解約の手続きを行います。
必要書類や手続き方法は、電力会社の公式サイトやカスタマーサポートで確認できます。
●ガス
各ガス会社(都市ガス、プロパンガスなど)に連絡し、同様に名義変更または解約の手続きを行います。
必要な書類や手続き方法については、ガス会社の公式サイトやカスタマーサポートで確認してください。
●水道
水道局または市区町村の水道部門に連絡し、名義変更または解約手続きを進めます。
市区町村によって手続き方法が異なる場合があるため、詳細は各水道局に確認します。
3.手続きの確認
手続き後、確認書類や手続き完了の通知を受け取ることができます。
確認書類が届くまで、各公共サービスの使用状況や料金に注意し、必要に応じて追加の連絡を行うことが重要です。
携帯電話、スマートフォンの解約
亡くなった方の携帯電話やスマートフォンの契約は、相続人であれば通信キャリアの店舗で解約できます。
各通信会社ごとに必要な書類が異なるため、事前に確認することが重要です。
電話番号を引き継ぎたい場合は、「承継」の申請が可能です。
NTTドコモ、au、ソフトバンクの大手キャリアはこの手続きに対応していますが、MVNO(仮想移動体通信事業者)が提供する格安ブランドについては事前に確認しておきましょう。
携帯電話やスマートフォンの契約解約手続き
1.必要書類の確認
通信キャリアによって必要な書類が異なります。
一般的に必要な書類は以下の通りです。
・故人の死亡証明書
・相続人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・故人の契約者番号や電話番号
各通信キャリアの公式サイトや店舗で、具体的に必要な書類を確認することが重要です。
2.通信キャリアに連絡
契約していた通信キャリアに連絡し、契約の解約手続きを依頼します。
店舗での手続きが一般的ですが、電話やオンラインでの手続きが可能な場合もあります。
3.店舗での手続き
通信キャリアの店舗に行き、必要書類を持参して解約手続きを行います。
店舗での手続きの際は、必要書類や本人確認のための情報を持参しましょう。
電話番号の承継
1.承継の申請
電話番号を引き継ぎたい場合は、「承継」の申請が必要です。
大手キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)では、この手続きが可能です。
2.承継手続きに必要な書類
・故人の死亡証明書
・相続人の本人確認書類
・承継を希望する方の契約情報(新規契約に必要な場合があります)
3.MVNO(仮想移動体通信事業者)の確認
MVNO(格安SIMなど)を利用している場合、承継手続きや解約手続きが異なることがあります。
MVNOの公式サイトやカスタマーサポートで確認し、必要な手続きを進めてください。
注意点
・通信契約の解約や承継は、相続人が行う必要があります。
・解約手続きが遅れると、月額料金が発生し続ける可能性があります。
・故人の携帯電話やスマートフォンに保存されているデータや連絡先などのバックアップを事前に取得することが望ましいです。
これらの手続きを迅速に行うことで、故人の携帯電話やスマートフォンの契約に関連する問題をスムーズに解決できます。
定期購読サービスなどの名義変更や契約停止
故人が生前に利用していた定期購読サービスやオンラインサービス(サブスクリプション型の動画や音楽配信など)の契約変更や停止手続きが必要な場合があります。
定期購読サービスやオンラインサービスの契約変更・停止手続き
1.契約情報の確認
亡くなった方が利用していた定期購読サービスやオンラインサービスを確認します。
情報は以下の方法で収集できます。
・クレジットカードの明細
・銀行の取引履歴
・メールの登録情報や受信した確認メール
・デジタルデバイス内のアプリケーションや履歴
2.契約先の特定
利用していたサービスの提供会社を特定します。
例えば、動画配信サービス、音楽配信サービス、新聞・雑誌の定期購読などがあります。
3.サービス提供会社に連絡
各サービス提供会社に連絡し、契約変更や停止の手続きを行います。
連絡方法は通常、電話、メール、またはオンラインサポートフォームを通じて行います。
4.必要書類の提出
契約停止手続きには、故人の死亡証明書や契約者の死亡を証明する書類が必要な場合があります。
サービス提供会社の指示に従って必要書類を提出します。
5.契約の解約
契約の解約や停止が完了したことを確認します。
解約確認書や停止確認のメールを受け取ることができる場合があります。
6.払い戻しの確認
前払いしていた料金や未使用のクレジットがある場合、払い戻しの手続きも確認します。
サービスによっては払い戻しに関するポリシーが異なるため、確認が必要です。
手続きの注意点
・情報の漏洩に注意
個人情報や契約内容を扱うため、慎重に取り扱い、必要な情報のみを提供するよう心掛けましょう。
・契約内容の確認
各サービスの契約条件や解約ポリシーを確認し、解約手続きに関する詳細を把握しておくことが大切です。
・デジタルサービスの確認
デジタルサービスは自動更新されることが多いため、手続きの漏れがないように注意しましょう。
これらの手続きを進めることで、故人の契約内容を整理し、余計な費用の発生を防ぐことができます。
SNSやメールアカウントの削除
亡くなった方が利用していたSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)やメールアカウントの削除手続きは、プライバシーとデータの管理を守るために重要です。
以下の手順で進めましょう。
SNSアカウントの削除
1.アカウントを特定
故人が利用していたSNSアカウントを特定します。
故人のデバイスでログイン状態や自動ログイン設定を確認するのも一つの方法です。
2.アカウント設定から削除
SNSのアカウント設定から「アカウントの削除」オプションを選択します。
手続きに従い、必要な情報を入力します。場合によっては、死亡証明書の提出が求められることがあります。
3.データのバックアップ
削除前に、故人のコンテンツやメッセージをバックアップしておくことが望ましいです。
思い出のデータが含まれている場合は、保存することを検討してください。
メールアカウントの削除
1.メールプロバイダに連絡
メールアカウントの削除には、メールサービス提供会社に直接連絡する必要があります。
故人の死亡を通知し、アカウントの削除またはデータ処理について手続きを進めます。
2.必要書類の提出
身分証明書や死亡診断書など、必要な書類を提出する場合があります。
手続きの詳細は、メールサービス提供会社の指示に従ってください。
データの管理
・データの保存
アカウント削除前に、故人のデジタルデータやコンテンツを保存することができます。
特別な思い出や重要な情報が含まれている場合は、バックアップを行うことが推奨されます。
・削除の確認
削除手続き後、アカウントが完全に削除されているか確認します。
削除するとデータが永久に消去されるため、慎重に進めることが重要です。
故人のデジタルプライバシーを守るため、アカウントの管理や削除手続きを適切に行いましょう。
遺族の心情や法的規制を尊重し、手続きを進めることが大切です。
遺品整理について

遺品整理は他の手続きや葬儀とは異なり、急いで済ませる必要がない場合が多いです。
故人が残した持ち物やデジタル遺品の整理は、慎重に行う必要があります。
以下のステップで遺品整理を進めてみましょう。
整理を始める時期を決める
遺品整理は、亡くなった方の遺品を整理する重要な作業ですが、精神的な負担も大きくかかります。
そのため、すぐに始めるのではなく、少し時間をおいてから取り組むのが良いでしょう。
時間を置くことで、親族の気持ちが落ち着き、整理に集中しやすくなります。
一般的には、遺品整理は葬儀直後ではなく、四十九日の法要やその後に親族が集まるタイミングで始めるのが良いとされています。
四十九日の法要は、故人の冥福を祈る大切な儀式であり、その後の親族が集まる場で遺品整理を始めることで、スムーズに進めやすくなります。
この時期に整理を開始することで、故人の思い出に対する感情も整理しやすくなります。
また、親族とのコミュニケーションを通じて、協力しながら進めることができるため、より良い遺品整理が実現しまう。
心の準備が整った段階で作業を開始することが、効果的な遺品整理につながります。
仕分け作業
遺品整理の主な作業は、不要な遺品と保管する遺品の仕分けです。
故人の持ち物すべてを対象とするため、一部屋丸ごと、または家全体の片付けが必要になることが一般的です。
セリの対象には、家具や衣類、本、写真など、様々な物品が含まれます。
れらの物品を保管するか処分するかを決定する作業が求められます。
特に重要なのは、遺品の中に紛れている重要書類や記録物を見つけ出すことです。
遺言書や保険証書、不動産の権利書、金融口座の情報など、これらの書類が見つかることで、後の手続きがスムーズに進むことがありますが、そのためには時間をかけて注意深く作業する必要があります。
遺品整理は感情的な面でも負担が大きいため、親族や友人と協力しながら進めると良いでしょう。
また、専門の遺品整理業者の利用も検討すべきです。
経験豊富な業者は、迅速かつ効果的に遺品整理を進めてくれます。
特に多くの遺品がある場合や時間的に余裕がない場合には、業者に依頼することで負担を軽減することができます。
優良な遺品整理業者の見つけ方をこちらの記事にまとめています。
あわせてお読みください。
遺品の搬出・後片付け
遺品整理では、故人の思い出を大切にしながら、不要な遺品を整理し、適切に処分することが重要です。
家財道具や衣類、文書などを遺族が一つひとつ仕分ける作業は時間と労力を要するため、遺品整理業者に依頼することで効率的に進められます。
また、自治体の戸別収集を利用したり、自分たちで処分施設に搬入したりする方法もありますが、業者に依頼することで搬出や分別の負担が軽減され、遺族の負担も大幅に減ります。
業者は経験豊富で、適切な処分方法やリサイクル、再利用の手配を行い、スムーズに遺品整理を進めるサポートを提供します。
まとめ
家族や身内が亡くなった際には、深い悲しみの中でも迅速かつ確実に手続きを進める必要があります。
この記事で紹介した手続きを参考に、少しでもスムーズに対応できることを願っています。
これらの手続きは多岐にわたり、時には複雑になることもあるため、弁護士や税理士、司法書士など専門家のサポートを検討することが大切です。
また、手続きの代行を引き受けてくれる遺品整理業者も存在します。
これらの業者は、遺品整理に加え、空き家の管理や活用、売却などの相談にも応じてくれるので、ぜひ問い合わせてみてください。
この記事では、家族が亡くなった後の手続と流れを時系列でわかりやすく紹介しました。
ご家族と一緒に確認したり、周囲で困っている方に教えたりして、ぜひお役立てください。