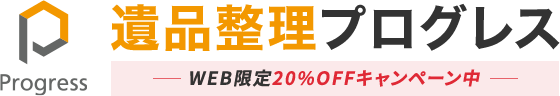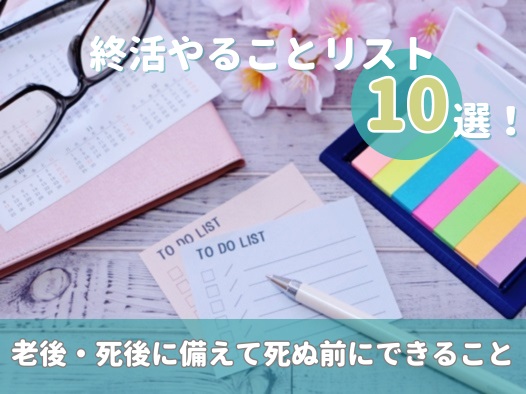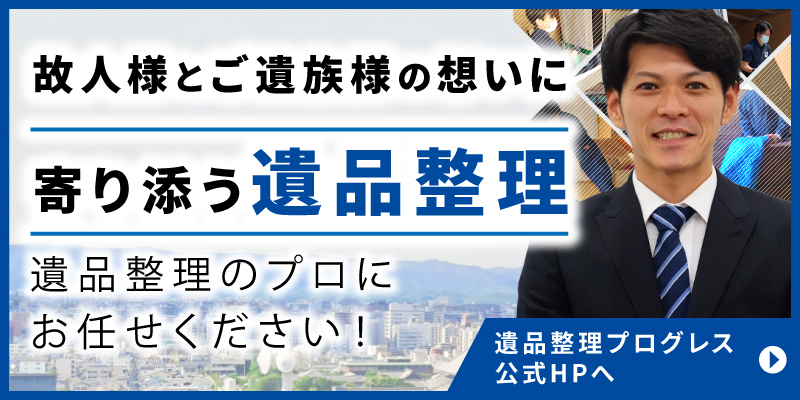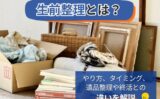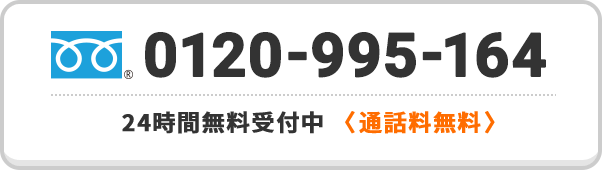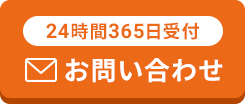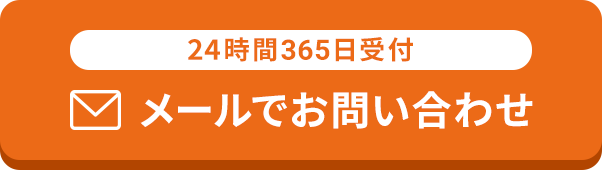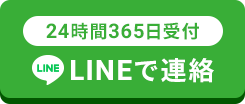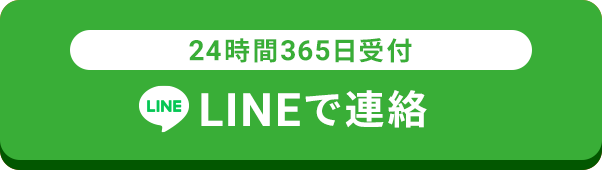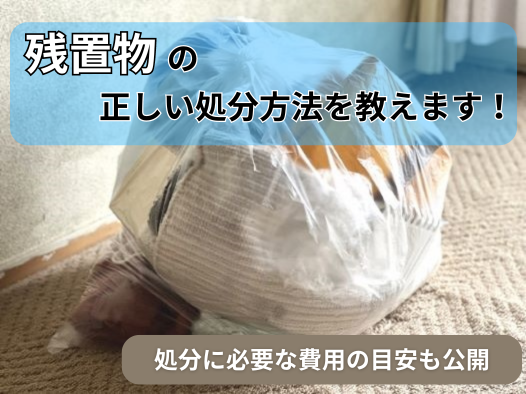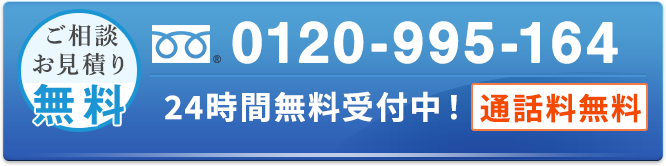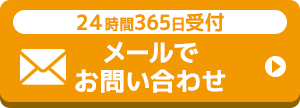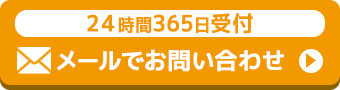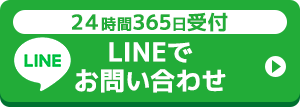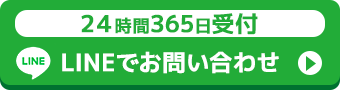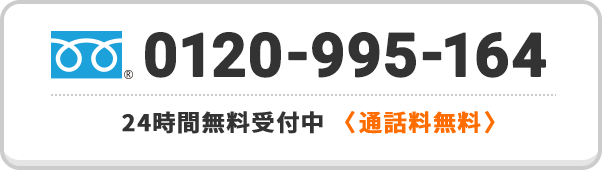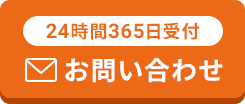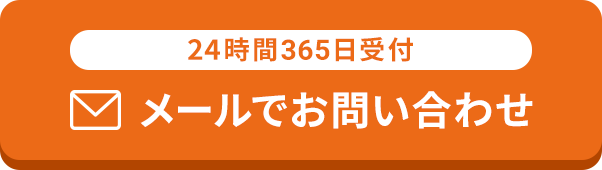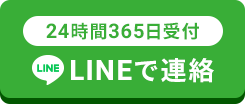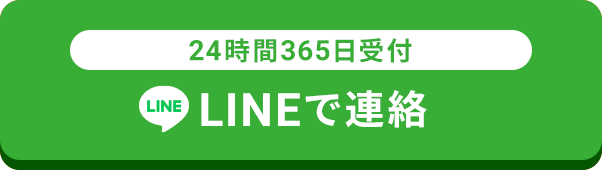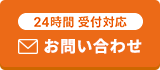「終活」は人生の最期を後悔せずに迎えられるように行う活動のことです。
いつかやろうと思っている人が増えていますが、具体的に何をすればいいのかわからないという人も少なくありません。
そこで、この記事では、終活でやることをリスト化してわかりやすく解説し、終活を行うメリットや注意点もご紹介いたします。
この記事は、上記の方々に有益な情報が満載です。
終活の重要性を理解し、具体的なアクションを取りたい方は、ぜひ参考にしてください。
終活やることリスト10項目 |
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
終活やることリスト10項目!リスト内容をわかりやすく解説
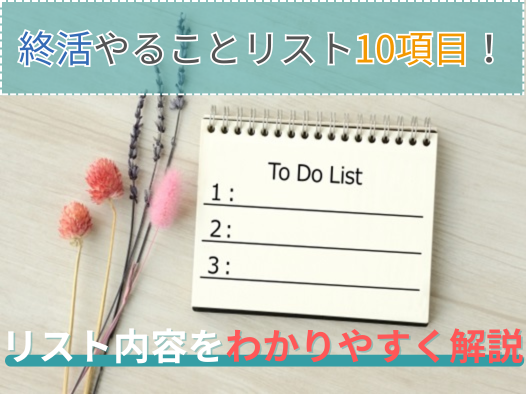
終活で行う10項目をわかりやすく解説します。
エンディングノートの作成
エンディングノートは「終活ノート」とも呼ばれ、その目的は個人情報や老後・死後の希望、家族や友人へのメッセージを整理して書き留めることにあります。
また、エンディングノートを書くことは自分史を振り返る良い機会とも言えるでしょう。
自分の中で優先度が高いものや、やり残していることが見えてきて、今後の人生設計を再構築しやすくなります。
エンディングノートに法的な拘束力はありませんが、病気や事故で判断能力を失ったり死亡したりした際に、家族への思いや要望を伝える有益な手段となります。
法律的な効力を持たせたい場合は、公証人による遺言書の作成を検討することが望ましいですが、エンディングノートはその補完的な役割を果たし、家族とのコミュニケーションを円滑にするツールとなります。
エンディングノートを通じて、より安心して未来に向き合うことができるでしょう。
財産の棚卸
自分で管理できなくなった場合や死後に備えて、所有する財産を一覧にした「財産目録」を作成しておくと安心です。
財産目録には、不動産や預貯金、株式、保険などの資産だけでなく、ローンや借金などの負債も詳細に記載します。
ローンや借金は相続の対象となり、相続人に支払い義務が引き継がれます。
借金がある場合は、その詳細を正確に記載することが求められます。
理想的には、自分自身で返済を進め、可能な限り負債を減らしておくことが賢明です。
また、使っていない銀行口座やクレジットカードなどはこの機会に解約しておきましょう。
・預貯金(銀行口座) ・不動産(登記簿) ・有価証券(株式、債券、手形など) ・生命保険(種類、保険会社名、連絡先) ・貴金属 ・ローン、借金 など |
これらを整理しておけば、いざというときに相続人がスムーズに相続手続きを進めることができ、トラブルを避ける助けになります。
老後資金の検討
2019年に金融庁が公表した報告書を基に「老後2,000万円問題」が持ち上がりました。
この2,000万円という金額はあくまでも最低限生活するために必要な資金の合計額です。
住宅の修繕費用や医療・介護費用、結婚や出産の祝儀などの支出は含まれません。
つまり、ゆとりのある老後生活を送るためには2,000万円では全く足りないということです。
老後資金シミュレーションを行っているサイトもあるので、自分の老後資金がいくら必要か調べてみると良いでしょう。
どれくらいの貯蓄が必要なのかがわかれば、今から対策を講じることもできます。
*参考サイト
老後資金はいくらあれば安心?計算方法と具体的な金額を解説(2023年:朝日新聞デジタル)
相続税対策
遺産の合計額が基礎控除額を上回る場合、その超過部分に対して相続税が課税されます。
相続税対策として「生前贈与」「生命保険への加入」などがありますが、詳しくは税理士など専門家への相談をおすすめします。
贈与のタイミングや方法、生命保険の契約内容など、細かな部分まで考慮して計画を立てることが重要になるため、適切なアドバイスを受けましょう。
相続は家族の大切な問題であり、税金の負担を軽減することは家族全体の利益につながります。
早めに対策を講じ、しっかりと準備を進めることが、安心して相続を迎えるための第一歩となります。
専門家の知識と経験を活用し、計画的に相続税対策を進めることが成功の鍵です。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
遺言状の作成
相続による親族間のトラブルを防ぐためにも、自身の意志を記しておきましょう。
遺言状は、項目や形式が法律で決められており、条件を満たさないものは法的拘束力がなくなります。
そのため、弁護士や法務省の公証役場に相談して作成することを推奨します。
遺言状には3種類ありますので、下記を参考にしてください。
自筆証書遺言:遺言者が書く。自筆で氏名・日付・遺言内容を書き、署名・押印する。 公正証書遺言:公証人及び証人(2人以上)の前で、遺言者が内容を口述し、それを公証人が筆記する。各人が署名・押印する。 秘密証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成封印し、封印された遺言書の封紙に公証人及び証人(2名以上)が署名・押印する。 |
持ち物・デジタルデータの整理
家財や生活用品など身の回りの品を整理し、不要なものは処分しましょう。
処分する方法としては、廃棄する以外にも家族や友人に譲る、リサイクルや寄付するなどさまざまな選択肢があります。
スマートフォンやパソコン内のデータ整理も忘れてはなりません。
重要なデータは、家族と共有するクラウドや外部デバイスに保存し、不要なデータは消去しておきましょう。
さらに、登録しているサイトのIDやパスワードも整理することが大切です。
これらの情報はエンディングノートに記載しておくと、万が一の際に家族がスムーズに対応できます。
また、使わなくなったアカウントは解約しておくことをおすすめします。
持ち物やデジタルデータの整理は、一度に全てを行うのは大変ですが、少しずつ計画的に進めることが重要です。
これにより、将来的なトラブルを防ぎ、家族への負担を軽減することができます。
人間関係の整理
しばらく連絡をとっていないけれど会いたい人、反対に我慢して付き合いを続けている人もいるでしょう。
限りある時間を自分や大切な人に使うために、人間関係を見直しましょう。
その一環として、「年賀状じまい(年賀状を送る習慣をやめること)」を行うのもおすすめです。
また、自分に何かあった場合にも家族から連絡してもらえるように、連絡先を記載した友人リストを作成しておきましょう。
人間関係の見直しには時間と労力が必要ですが、その結果、より充実した人生を送ることができます。
自分の時間とエネルギーを大切にし、本当に価値のある人間関係を築くために、少しずつでも見直しを進めていきましょう。
適切な整理を行うことで、心の負担も軽減され、自分らしい生き方を実現する手助けとなります。
葬儀・お墓の準備
葬儀やお墓の希望を事前に伝えることで、家族の負担を大幅に軽減できます。
まず、葬儀については、参列してほしい人の名簿や連絡先をリストアップしておきましょう。
また、希望する宗派や供養方法、生前予約している葬儀社がある場合は、その連絡先を家族に伝えておきましょう。
遺影用の写真もあらかじめ準備するか、使ってほしい写真を選んでおくと安心です。
次に、お墓の希望についても家族と話し合いましょう。
先祖代々のお墓に入るか、別の供養方法を希望するかを決めます。
自分でお墓を購入している場合は、その場所や連絡先を家族に知らせておきましょう。
また、お墓を持たない供養方法も検討できます。
希望や予算に合わせて、メリット・デメリットを踏まえたうえで最適な方法を話し合って決めておきましょう。
永代供養:家族に代わりお墓の管理をしてくれる方法で、希望の回忌まで管理してくれる。 樹木葬:樹木や草花を墓標として埋葬する方法。 海洋葬:遺灰を指定の海や湖に散骨して供養する方法。 宇宙葬:遺灰を納めたカプセルをロケットに乗せて打ち上げる方法。 |
医療・介護の希望
医療・介護の常用している薬やかかりつけ医の情報、加入している医療保険などを記載しましょう。
万が一のときに医師や薬剤師が適切な治療を行う際の参考となりますし、保険の内容をまとめておけば、治療費の請求や保険金の手続きをスムーズに行うことができます.
また、延命治療や臓器提供についての希望も家族に伝えておくことが大切です。
自分の意志を明確にしておくことで、自分が意識不明の状態や末期状態になったときに、家族が判断に迷うのを防ぐことができます。
さらに、意思疎通が取れない状態や介護が必要になった場合に入所したい施設や、用意している費用の情報があれば、いざという時に家族もすぐに対応できます。
介護施設の見学や相談を事前に行い、自分に最適な環境を選ぶことも老後の備えとして非常に重要なのです。
今後の人生設計
日々の忙しさに追われているうちに忘れてしまっていた「やりたいこと」を、終活を通じて再確認する方も多くいます。
自分が挑戦したいことや叶えたい夢を書き出し、これからの人生の目標や意義を明確にすることが大切です。
終活は単なる手続きの一環ではなく、自己探求や成長の機会でもあります。
自分の人生で何が本当に重要であり、それをどう実現していくかを考えることで、より充実した人生を送るための方針を明確にしていくことが、終活の真の意義であり目的でもあります。
終活を行うメリット!自分も家族も嬉しいことがいっぱい

終活をするメリットを知れば、ますます意欲的に終活に取り組めるでしょう。
悲しい別れの時に遺品整理や手続きをしなくても済むことは、遺族にとって大きな負担軽減となります。
遺言書を作成しておくことで相続トラブルを未然に防ぎ、家族が円満に手続きを進められる安心感も得られます。
また、不要な品物を整理することで住環境が整い、生活の質が向上します。
さらに、災害時のリスクも減少するため、安全で快適な暮らしを築く助けになります。
終活は人間関係や将来設計を見直すきっかけとなり、自分自身や家族のために大切なことを再確認する貴重な機会です。
これにより、充実した人生を送るための準備を整えることができます。
終活を効率良く進めるためのポイントと注意点!

終活は無理をせず、楽しんで行うことが大切です。
終活を効率良く進めるためのポイント
終活を始める際のアプローチとして、体力が必要なことから始めることがポイントです。
持ち物の整理や不用品の処分は時間と労力がかかりますし、介護施設やお墓の選定には多くの見学が必要です。
そのため、体力的に元気なときから早めに取り組むことが重要です。
もし体力が必要なことをする気にならない場合は、できることから始めるのも有効です。
例えば、エンディングノートの作成や友人のリスト作りから始めてみましょう。
自分にとって取り組みやすい項目から進めれば、終活がよりスムーズに進行します。
また、要不要の判断に迷ったら、一旦保留にして時間を置くこともおすすめです。
数カ月から1年程度の間をおいてから再考すると、使う機会があるかどうかがより明確になります。
冷静に検討することで、必要なものと不要なものを見極めることができます。
これらのアプローチを組み合わせて、終活を進める計画を立ててください。
終活をする際の注意点
終活をする際の注意点はいくつかあります。
前向きに取り組むことが大切です。
できる範囲から始めて、将来の不安や家族への負担を減らしましょう。
快適な住まいになることや自分史の振り返りなど、楽しい側面にも焦点を当てて前向きに進めてください。
また、気長に取り組むことも重要です。
一気に進めるのは負担が大きいので、日常生活に支障が出ない範囲で自分のペースで進めましょう。
さらに、家族と情報を共有することも忘れてはいけません。
エンディングノートや遺言状を準備しても、家族がその存在を知らなければ意味がありません。
定期的に家族と共有し、意思を明確にしておきましょう。
家族や親族にも介護や医療、相続についての要望や意見があるかもしれませんので、自分にとっても大切な人たちの意見をきちんと受け止めて話し合うことも大切です。
最後に、終活は一度やって終わりではなく、定期的な見直しが必要です。
自分の状況や気持ちが変わることもあるので、1年に1回や3年に1回などのペースでエンディングノートを見直し、必要に応じて更新しましょう。
終活やエンディングノート作成のご相談も、遺品整理プログレスへ!
終活を始めるのに最適なタイミングは?早いほうがいい?
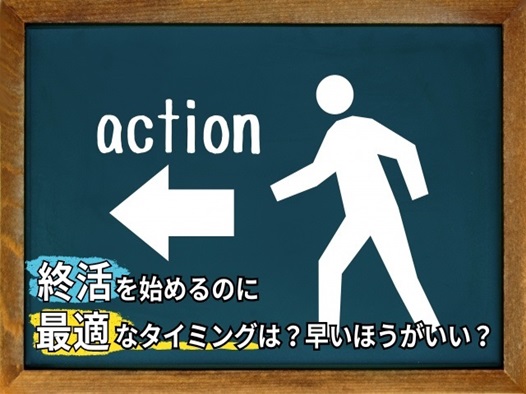
近年、終活に対する関心は年齢を問わず高まっています。
終活を始める時期に決まりはありませんが、体力や判断力が必要な作業が多いことから、できるだけ早く始めることが重要です。
筆者は「今」が始め時だと考えていますが、人生の節目やターニングポイントを機に始めるのも良いでしょう。
楽天インサイト株式会社の調査によると、「終活を行っている・行う意向がある」人は約7割に上ります。
特に20代や30代の若い世代でも平均5割を超えています。
終活を始めるきっかけとしては、「自分の健康に不安を感じたこと」が最も多く、特に40代や60代で顕著です(40代:22.4%、60代:28.2%)。
さらに、20代では「生涯独身だろうと思ったこと」(17.1%)、30代では「子供ができたこと」(23%)、50代では「家族や大切な人が亡くなったこと」(25.4%)が終活に向けた動機として挙げられています。
このように、終活は個々の人生の段階や経験によって異なる意義を持ち、年代を超えて関心を集めています。
*参考サイト
「終活」のきっかけは、20代で「生涯独身だろうと思ったこと」、30代で「子供ができたこと」がトップ 終活に関する調査(楽天インサイト株式会社:2024年)
終活のアレコレを相談したい!お悩み別の相談先をご紹介

一言で終活と言ってもその内容は多岐にわたるため、何に困るかは人それぞれです。
簡単にまとめると、終活に関するすべての悩みを幅広く相談できるのは、生前整理アドバイザーや遺品整理・生前整理業者です。
相続税や介護のことなど、より専門的な悩みなら税理士や地域包括支援センターなどに相談するのが良いでしょう。
この章では、終活のお悩み別にどこに相談すれば良いかをまとめています。
|
終活のやり方を教えてほしい |
市区町村役場の相談窓口、終活イベント・終活セミナー、遺品整理業者・葬儀社などが主催の民間の終活相談 |
|
荷物の仕分けや不用品の処分について相談したい |
生前整理アドバイザー、遺品整理・生前整理業者 |
|
老後の資金について相談したい |
ファイナンシャルプランナー、銀行の窓口 |
|
葬儀やお墓のことを詳しく聞きたい |
葬儀業者、冠婚葬祭互助会、寺院、霊園 |
|
介護について相談したい |
地域包括支援センター(高齢者あんしん相談センター)、市区町村役場や社会福祉協議会の相談窓口、医療機関 |
|
相続に対する不安や悩みを相談したい |
税理士、弁護士、司法書士 |
・おひとり様こそ終活はおすすめ
終活はすべての人にとって有益です。
特に、おひとり様の場合は、看病や介護が必要になったときに頼れる人がいないという心配や孤独死の不安もあります。
終活を行う際に、法定後見制度や任意後見制度を利用して備えておくと、万が一の時にも安心です。
*参考サイト
まとめ
家族がいない、または資産が少ないからといって終活をしないと考える人もいます。
しかし、そのような方ほど、将来に備えて準備を整えておくことが重要です。
介護や死後の手続き、そして葬儀の準備は、役所や社会的な制度を利用することで十分可能です。
終活はただ単に自分の将来を考えるだけでなく、周囲への負担を減らすことにもつながります。
頼れる人が周りにいなくても、生前に準備をしておけば、いざという時の安心感を与えてくれます。
自分の意志を明確にすることで、未来に備えることができるのです。