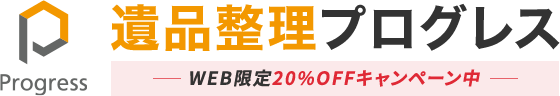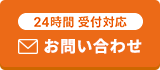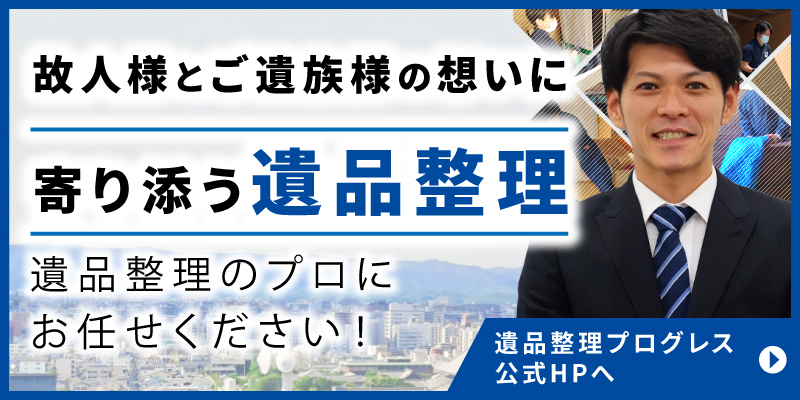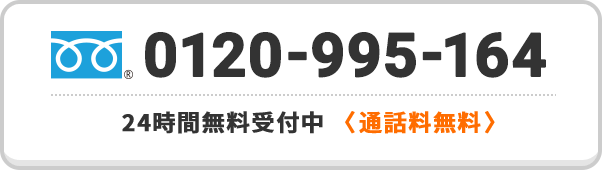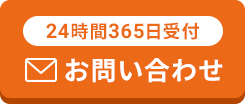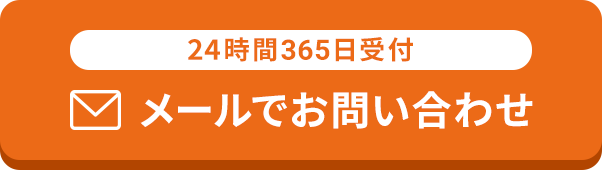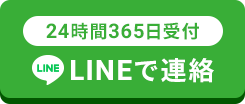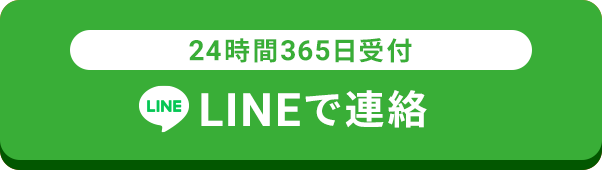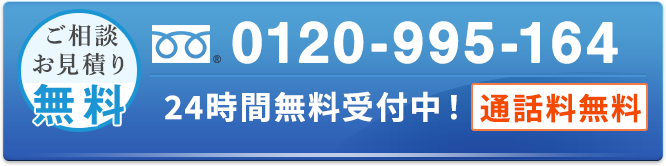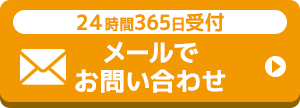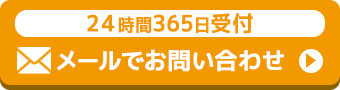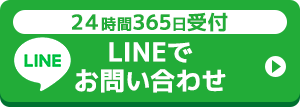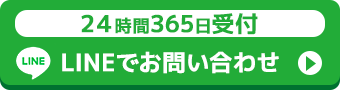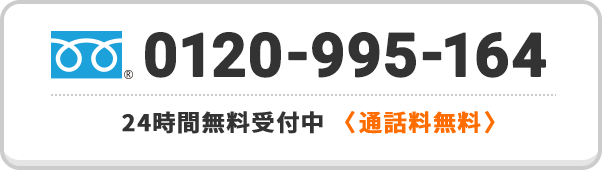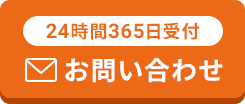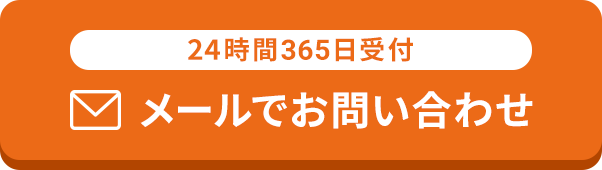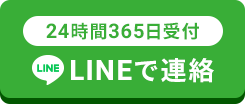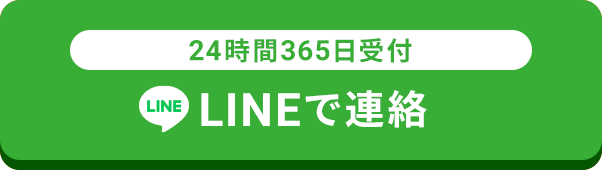先日「日本人の10人に1人が80歳以上」というショッキングなニュースが出ました。
総務省の発表によると、65歳以上の高齢者は総人口の29.1%と過去最高を記録しており、日本の高齢者人口の割合は世界で最も高いそうです。
2040年代には多死社会を迎えるとされる日本において、孤独死問題も他人事ではありません。
「一人暮らしの自分が亡くなったら、後のことはどうしよう」「一人暮らしの親戚がいるが、亡くなった後、どう対応したら良いのだろう」と考えて不安になることはありませんか?
こちらのコラムでは孤独死に対する疑問にお答えするとともに、一人暮らしで亡くなった場合に起こり得る問題や遺品整理のやり方について解説いたします。
*参考サイト
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
一人暮らしで亡くなったらどうなる?

この章では、「遺品整理は誰がするのか」「発見が遅れた時は?」など、誰もが疑問に思うことにお答えします。
孤独死Q&A
Q1:発見した場合はどうしたらいい?
A1:生死の判断がつかない場合は救急車を呼びます。
亡くなっている場合は警察へ通報を。
警察が現場検証・検視を行い死因の特定や事件性の有無を判断します。
警察からの許可が出るまでは、遺体を動かしたり部屋の中の物を移動してはいけません。
Q2:遺品整理は誰がするの?
A2:基本的に遺族(配偶者・親・子・兄弟姉妹・祖父母・内縁者含む)が故人の遺品整理を行うことになります。
身寄りがない場合には、役所が故人の戸籍をたどって親族を探して連絡します。
しかし賃貸マンションやアパートの場合は、相続人や賃貸の連帯保証人でなければ、賃貸契約の解除や入室して遺品整理を行うことができません。
遺族が相続人や連帯保証人でない時は、相続人または連帯保証人に連絡を取る必要があります。
Q3:発見が遅れるとどうなるの?
A3:死後の経過時間が長いほどご遺体の腐敗が進み、漏れ出した体液で床などが汚れ、シミや腐敗臭が染み付いてしまうこともあり、害虫が大量発生するケースも少なくありません。
悪臭や害虫が近隣に広がったり、ウイルス感染したりする危険性もあるため、入室はもちろん、窓や扉を明け放すのも厳禁です。
原状回復するには”特殊清掃”が必要になります。
一人暮らしで亡くなった場合に起こり得る5つの問題
.jpg)
遺産を把握するのが大変
現金・預貯金・保険・有価証券・不動産など、故人の財産の中で資産価値があるものを遺産といいます。
本人の死後、どれだけ遺産があるのかをすべて把握するのは大変で、調べるのにも時間がかかります。
スマートフォンやパソコンのデータも確認しなければならず、パスワードがわからなくて困ったという事例もよく耳にします。
借金・ローン・未払い金などのマイナスの財産も遺族に引き継がれるので、これらも把握することが必要です。
遺産・遺品・不用品の区別が難しい
興味のない人からみると不用品に見えるものでも、実は金銭的に高い価値のある品だったということもあります。
金銭的価値のあるものなら相続財産ということになり遺産です。
誤って捨ててしまうことが無いように気を付けなくてはいけません。
また金銭的価値は無く、一見すると不用品に見えるものでも、遺族の誰かからすると故人との思い出が詰まった大切なものかもしれません。
形見分け品なのか不用品なのか、といった判断はとても難しいものです。
遺品量が多い
高齢になると体力も落ちてマメに掃除や片付けができなくなってきます。
中には、収集グセや認知症による影響で物が捨てられなくなる人もおられます。
そうなると遺品量は多く、遺族は整理に苦労することになります。
故人が実家暮らしの場合、親や兄弟の遺品もそのまま残っていて、さらに膨大な量になっていることもあるのです。
遺品整理にかけられる時間が少ない
故人の住まいが賃貸だった場合、多くは月末までに退去しなくてはいけません。
遺族が賃貸契約を延長できることもありますが、その分の費用がかかります。
汚損が激しい
発見が遅れたケースほど部屋の汚損は激しく、原状回復が困難になり、修繕費用も膨れ上がります。
遺品整理のやり方と注意点
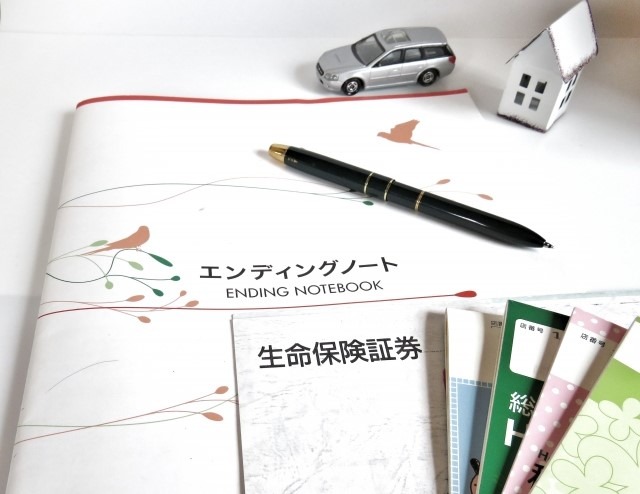
スムーズに遺品整理を進められるよう、やり方と注意点をご説明します。
遺品整理のやり方
1:遺産をすべて確認する
預金通帳・有価証券・生命保険証書・土地の権利書・借用書など、相続に必要な書類をまとめます。
近頃はネットバンク口座やネット証券口座なども多いので、スマートフォンやパソコンも忘れずに確認し、すべての遺産を把握しましょう。
2:各種手続き・届出を行う
死亡届の提出や火葬許可証の発行、葬儀の手配、健康保険証・運転免許証の返却、各種契約の解約などの手続きを行います。
3:遺品の仕分けを行う
形見分けするものと不要なものをわけていきましょう。
写真やビデオなどはデータにして残す方法もあり、保管スペースを大幅に減らすことができます。
4:供養が必要な遺品の整理
仏壇や神棚などの宗教的なものは菩提寺や檀那寺の住職、氏神神社の神職に相談し、処分方法を確認しましょう。
仏壇は「御霊抜き(みたまぬき)」を行い、神棚は神様に神社へお帰りいただいたら、後はゴミとして処分することができます。
他にも、故人の愛用品や思い出の品の供養も可能です。
お寺や神社以外にも、遺品供養専門業者や遺品整理業者が対応してくれます。
遺品整理の注意点5つ
・他の親族に相談せずに遺品整理を行うと、後々トラブルになることも。
親族間で遺品整理を行う日程や残す品物について話し合ってから始めましょう。
・遺言状やエンディングノートがないか確認を。
遺品の処分方法や相続についてなど、故人の要望が書いてある可能性があります。
・死亡届は「死亡を知った日から7日間」の期限内に提出。
期限に遅れると5万円以下の過料が科せられる、または葬儀や埋葬ができない場合もあります。
・故人が社会保険に加入していた場合には「埋葬料」が、国民健康保険に加入していた場合には「葬祭費」が給付されますが、被保険者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ無効になるので、忘れないうちに早めに申請しましょう。
・特殊清掃が必要な場合は、それにかかる費用をマイナス資産として計上することができます。
遺産相続権を持つ親族が複数人いる中で、特殊清掃費用が依頼者一人の負担になってしまわないよう遺産分配前に確認しましょう。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
専門業者に依頼するメリット

自分では難しいと感じたり、孤独死のあった部屋に入るのが精神的につらいと感じるようなときには専門業者へ依頼するのがよいでしょう。
以下に、専門業者へ依頼するメリット3つをご紹介します。
スピード解決が叶う
遺品整理はもちろん、不用品の回収、遺品の供養なども行っているため、自分で行うより断然速く解決できます。
業者によって手掛けるサービスの幅は様々で、不用品買取やハウスクリーニング、リフォーム、その他関連サービスを一括で請け負っているところもあります。
「忙しくて時間が取れない」「遺品量が多すぎて手に負えない」「内装リフォームもしたい」という人には、業者への依頼をおすすめします。
遺品整理士へ相談できる
遺品整理士資格は遺品整理を行ううえで必須の資格ではありませんが、取得していると、遺品を取り扱う際の心構えや整理の手順・方法、関連する手続きに対しての知識などを一定水準以上持っていることの証明になります。
遺品整理士が在籍している業者へ依頼すれば、わからないことも相談できるので安心です。
汚損が激しい部屋も任せられる
ご遺体の発見が遅れた場合、腐敗が進み、漏れ出した体液や腐敗臭がこびりついていたり、害虫が大量発生していたりすることもあります。
このような状態では、感染症リスクもあるため対策なしに入室するのは危険なうえ、通常のハウスクリーニングでの原状回復は見込めません。
「特殊清掃」や「害虫駆除」の技術を備えている専門業者に任せましょう。
遺品整理業者への依頼は、ご自身の都合と現場状況、予算を鑑みて検討しましょう。
遺品整理の費用は、部屋の広さと遺品量で決まります。
料金体系は業者によって様々で、「トラックの荷台に積み放題でいくら」とする業者や、基本料金以外に「運送料」「人件費」「植木処分費」などの追加料金がかかる業者もあり、実際にいくらかかるのかは現場を確認したうえで見積もりを出してもらわなければわかりません。
予算内に収まるのかを知るためにも事前に詳しい見積もりを用意してもらいましょう。
優良業者を見極めるポイント

残念なことですが、遺品整理業者の中には悪質な業者も存在します。
初期見積もりは安かったのに、後から法外な費用を請求されたり、本当は資産価値があるものを処分品として回収し、勝手に売却して利益を得ていたり、遺品の不法投棄や盗難をされたりなど、度々被害が報告されています。
悪質な業者を選んでしまわないように、遺品整理業者を見極めるポイントをお伝えします。
見極めポイント6つ
・ホームページの作りが丁寧で会社概要や所在地が記載されている
・口コミやサービス体験者のリアルな声が多く信用性がある
・料金設定が明確で、見積りが詳しくわかりやすい
・必要な資格はもちろん、関連資格も持っている
・少なくとも3社以上から相見積もりを取り比較する
・相見積もり依頼やプラン内容の説明を求めても気持ち良く対応してくれる
まとめ
身近な人が孤独死されたとなると、そのつらさや悲しみに胸が締め付けられ、すぐに前を向くことは難しいかもしれません。
それでも、発見が遅れた孤独死の場合ほど早急に対応しなければいけないのです。
それならば、そもそも孤独死を「しない・させない」ために、生前から対策を講じるのが賢明でしょう。
マメに連絡を取り合う、行政や民間の見守りサービスを利用する、地域のコミュニティに参加するなど、一人暮らしの人が孤立してしまわないようにする工夫が大切です。
そこまでしても、孤独死の可能性を完全に無くすことはできません。
だからこそ、いつ最期を迎えることになっても後悔のないように、また今後の人生をより充実して過ごすためにも”生前整理”を行うことを筆者はおすすめいたします。
*関連コラム