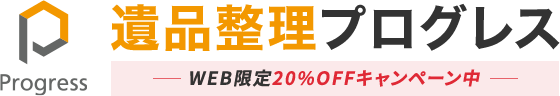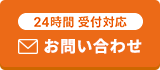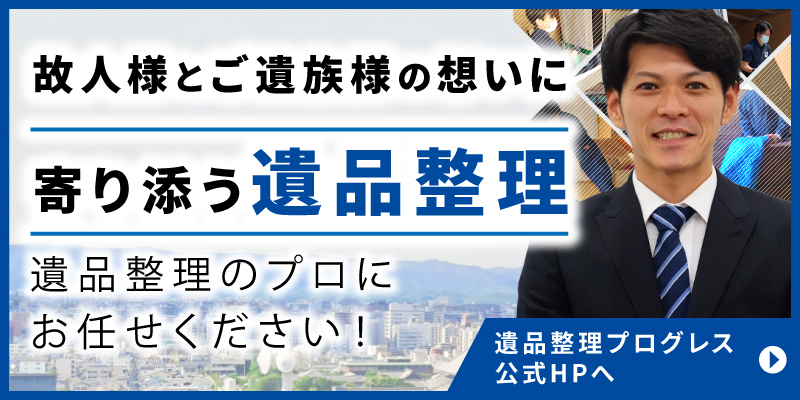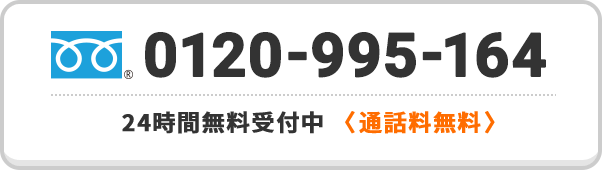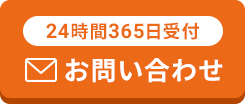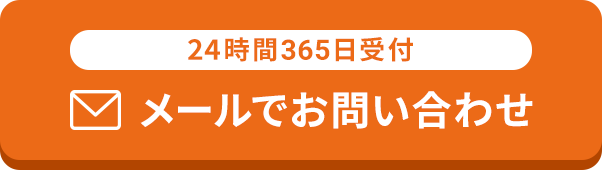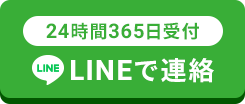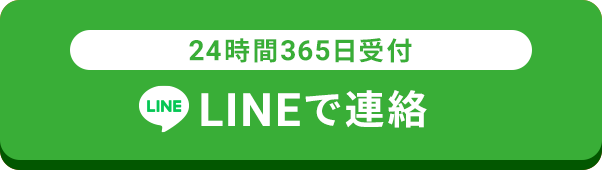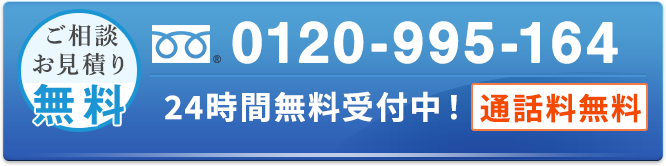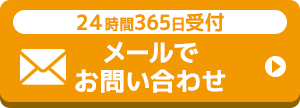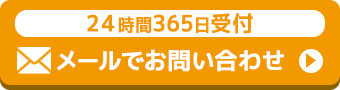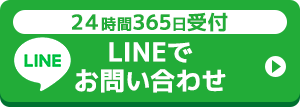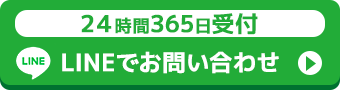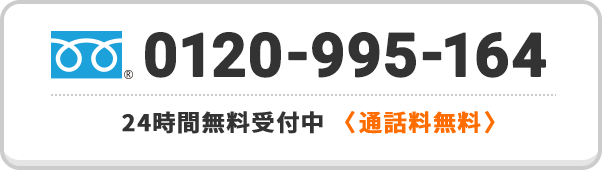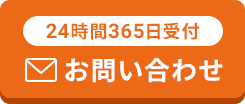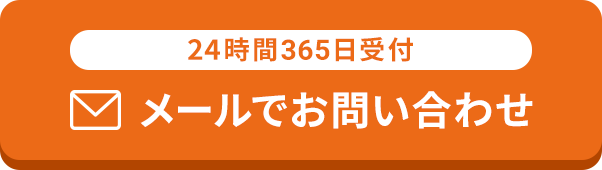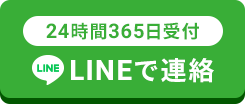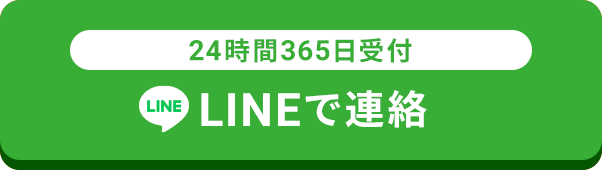遺族や親しい人に形見分けされる物は、故人が趣味で使用していた道具、アクセサリーなど、金銭価値が低い物がほとんどです。ですが、遺品の種類によっては価値の高さ、希少性などが後に発覚し、親族間でトラブルに発展する場合もあります。
故人が残した物で親族同士の絆が切れてしまわないように、今回は遺品を形見としてもらうときに気を付けることをまとめました。
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
遺品をもらう理由とは何?形見分けは何のために行う?

遺品をもらうと故人との思い出を偲ぶ拠り所になってくれます。
形見分けとは、故人が愛用していた物、収集していた物を親族やお世話になった人に譲る習慣のことです。
あるいは遺品整理中に、ゴミとして処分するには忍びない物が出てきたときに誰かに譲って使ってもらう目的もあります。
指輪やネックレスだけでなく、衣類やカバン、万年筆など、形見分けの物は何を譲っても構わないとされています。ただし、壊れている物や穴が開いている物はもらっても使用用途がありませんので、断るか処分を手伝うようにしましょう。
遺品はいつからあげたりもらうべき?相談する日も考慮しよう

形見分けは亡くなってから49日の忌明けの間に行うべきと言われています。49日の間は法要のために親族や故人と深い交友関係のあった人が集まり、相続についての相談が行いやすい期間といえます。
形見分けを始める前に、遺産の総額を確認したり、相続人同士で遺産の分割について打ち合わせをしておきましょう。事前に意思を確認しておけば、相続トラブルを回避できます。
形見分けに相応しい時期は宗派によって異なります。仏式では49日の間に行いますが、神式の場合は50日が経過した後、キリスト教では30日が経過した後が目安になります。
遺品をもらうときに起こりやすいトラブルとは?対策方法を解説

形見分けは単なる不用品の譲渡ではありません。相続に関する問題や遺品の持ち逃げ、相続税、贈与税の申告漏れなどのトラブルに注意しなければいけません。
遺品の価値による相続問題
一目では希少性がわからない遺品に高い価値のあると発覚し、相続トラブルに発展してしまう場合があります。
また、献身的に介護を行った相続人には「寄与分」として、本来の法定相続分よりも多めの遺産を相続できる制度があります。
しかし、寄与分を認めてもらうためには献身的な介護を行った裏付けの資料が必要になります。献身的な行動は数字では表しにくく、「私はこんなに世話をした」「あなたはしていない」と親族同士で感情的な対立が発生してしまいます。
遺品の価値は相続をする前にご自身で調べ、価値の高い物は遺産として親族間で話し合いをして譲り受けるようにしましょう。
知らない人による遺品の持ち逃げ
49日の期間中、知らない人が突然現われ、「故人と親しくしていたから遺品を譲ってほしい」と頼んでくる場合があります。本当に故人と親しかった人である場合もありますが、形見分けの物を貰おうとしている赤の他人の場合もあります。
安易に遺品を渡すことは絶対に避けてください。
遺品をすぐに渡さず、まずは故人との関係性を調べましょう。エンディングノートを確認したり、ご自身が把握している故人の他の友人に尋ねたりして調べます。
関係性が確認できなかった場合は、渡せる形見がない、または親族のみで行っていると伝えて断るようにしましょう。
相続税の申告漏れ
高額な遺品を形見分けしてもらい、後で相続税の申告を忘れてしまうトラブルにも注意しなければいけません。
不動産や骨董品など、価値が高い遺品を相続すると相続税が発生する場合があります。
相続税は3,000万の基礎控除があり、5万円以下など少し高価な遺品を相続した場合は発生しません。
しかし、相続税の申告は死亡後から10カ月以内に済ませなければいけません。
申告を忘れてしまうと加算税や延滞税が課せられることがほとんどですが、脱税として刑事罰を受ける場合もあります。相続税や贈与税の申告でわからないことがあれば、税理士などの専門家に相談をしてみましょう。
刀剣、銃を相続した場合の届け出忘れ
軍刀や拳銃、猟銃などの銃砲刀剣類を無許可で所持することは禁止されています。骨董品として譲り受ける場合も警察に登録証を届け出る必要があります。
登録証とは日本刀が美術品、骨董品としての価値があると国が認めた証として発行される公文書です。
登録証の届け出をしないまま所持していると銃刀法違反によって罰せられたり、暴発事件につながる可能性があります。
登録には審査が必要となり、一つの刀剣、銃につき登録審査手数料が必要となります。
猟銃や拳銃などは銃砲所持許可を取得している人に譲るか、販売店などで廃棄処分をしてもらいましょう。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
形見分けのマナーとは?相手によい印象を与えるもらい方と渡し方

ご自身が遺品をもらった場合ですが、基本的にお礼の品や手紙を送る必要はありません。代わりに故人を偲び、感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
ご自身が遺品を故人の代わりに渡す場合は、品物が壊れていないか、汚れていないかを入念にチェックします。衣類であればクリーニング、カメラなどの精密機器であればメンテナンスをしてから渡しましょう。また、故人から見て目上の人には遺品を贈ってはいけないとされています。どうしても渡してほしいと故人に頼まれた場合以外は譲渡しないようにしましょう。
渡す遺品を化粧箱に入れたり包装をしたりする必要はありません。半紙のような白い紙に包む、あるいは香典用の紙袋に入れて渡すなど、簡易的な包装に留めるようにしてください。
遠方にお住まいの方に遺品を渡したい場合は、郵送しても問題ありません。その場合は形見分けである旨を手紙に書いて遺品に添えておくと、相手に良い印象を与えることができます。
そして、相手に身に覚えのない贈与税の支払いをさせないよう、高価な物は送らないようにしましょう。貴金属の譲渡はトラブルが発生してもすぐに解決できるよう、親族間のみで形見分けを行うことがおすすめです。
所持したくない遺品をもらった場合はどうすればいい?

ぜひもらってほしいと強引に押しつけられたものの、遺品をもらうことに抵抗がある方がいらっしゃるかもしれません。
その場合は、一般ゴミとして処分するのではなく、別の方法で遺品を手放しましょう。
故人が大切にしていた趣味の道具やコレクションはなるべく手元に残してあげたいですよね。
遺品の写真を撮り、データ化することでいつでも見返すことができます。着物やアクセサリーなどは日常使いができる小物や流行のデザインにリメイクして所持することもおすすめです。
趣味の道具であれば、その形見の価値を理解し、大切に使ってくれる方に譲渡するのも良いでしょう。
形見を処分すると故人に対して失礼になるのではないかと罪悪感を感じてしまう場合があるかもしれません。その場合は神社やお寺でお焚き上げや合同供養をしてもらうことで心残りのないお別れができます。
故人の遺品を片付けないまま放置するよりも、大切な人が亡くなった事実に向き合って整理する気持ちが供養につながります。
管理が難しい遺品は感謝の気持ちを込めてお別れをしましょう。
故人と血縁関係がないのに、遺族から形見を贈られた場合は?
故人と深い交友関係があり、遺族より「受け取ってほしい」と申し出があった場合は、受け取ることが礼儀とされています。
ですが、遺品には着物や楽器など定期的なお手入れが必要な物や、彫刻や家具などの大きな物も含まれます。
管理が難しい遺品を形見として引き取ってもらえないか相談される場合もあるかもしれません。
ご自身の手でやむを得ず処分することを避けるためにも、管理し続ける自信がない場合は失礼のない範囲で辞退をするのも大切です。
遺族より受け取った遺品は第三者に譲渡したり売ったりせず、自宅で大切に保管するか、供養という形で手放しましょう。
まとめ
遺品をもらったときは故人を偲び、感謝の気持ちを忘れず大切に保管しましょう。
生きている間に遺産や愛用品の譲渡先を確認しておくことで、持ち主の意思を尊重しトラブルなく形見分けが行えます。生前整理で必要ないと判断した貴金属、高級品があれば、換金して今後の生活費用や介護費用に充ててしまうのも良いでしょう。
遺品の片付け、相続について何も決めていないという方はこの機会に形見分けについて話し合ってみましょう。