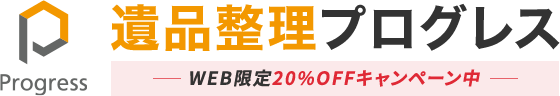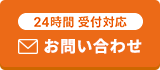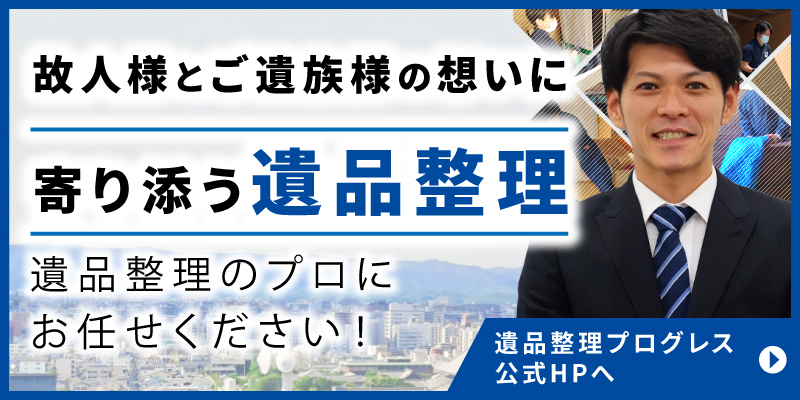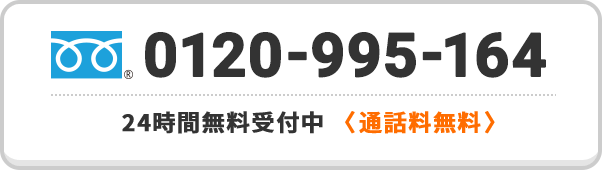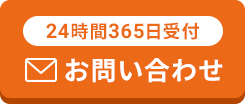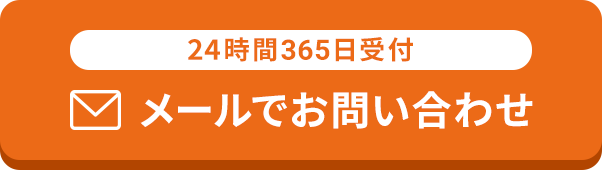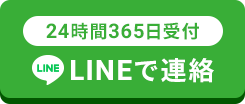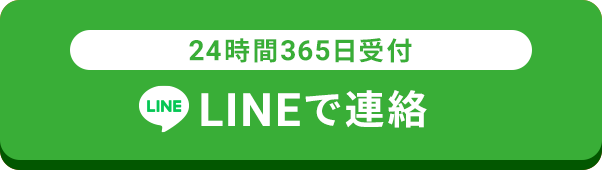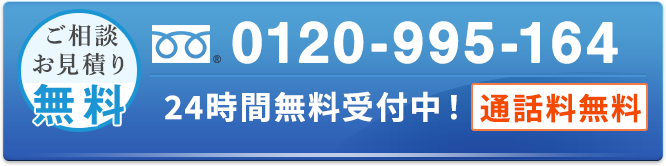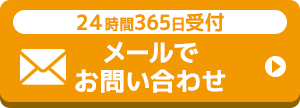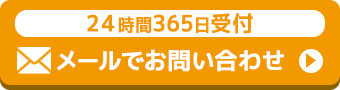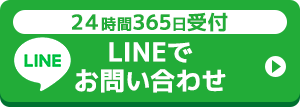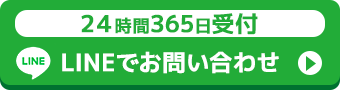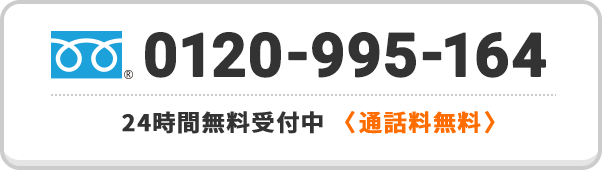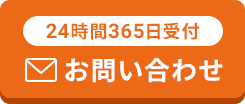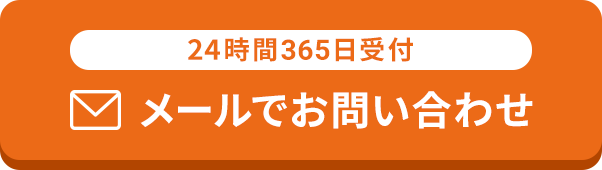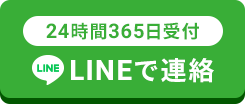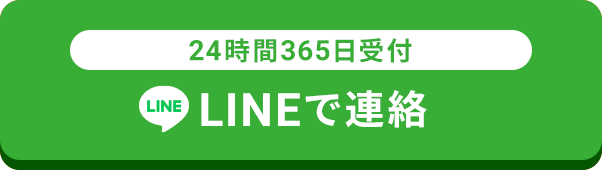生前整理は、年齢に関係なく誰もが始められます。
だからこそ「どのタイミングで始めればいいのか」が分からなくなります。もし始めたとしても、何をどの順番で進めていけばいいか分からず、途中で片付けをやめてしまうかもしれません。
「いつ」「どのような流れで」行うかを事前にはっきり決めておけば、生前整理はスムーズに進められます。
今回は、生前整理を効率良く進めるためのポイントを5つまとめましたので、始めるときの参考にしてみてください。
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
生前整理をいつ始めるか決める

生前整理を始めるタイミングは「何歳から」と明確には決まっていません。ですので、いつ始めてもかまいません。ただ「今は取りかかる余裕がない」という方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合は「人生の節目」に行うと良いでしょう。
定年退職、子供が結婚したとき、配偶者が亡くなったときなど、いずれも、自分の時間にゆとりが持てるようになったり、物の整理をまとめて行えるようになったりするタイミングです。
人生に何かしらの変化があったときに生前整理を始めてみてはいかがでしょうか。
身の回りの物を整理する

生前整理を行う際、まずは身の回りの物の整理から始めていきましょう。
身の回りの物は、以下の手順で行うと効率良く整理できます。
①必要な物と不要な物を分別する
長年愛用した家具家電、着なくなった衣服、結婚時に買ったアクセサリー…… どれが必要でどれが不要なのかをハッキリさせることは、整理整頓の基本でもあります。
また分別の際、「いる」「いらない」ではなく「使う」「使わない」で分別するよう心掛けましょう。
「これはいつか使うだろうから、いる」 「これは捨てたくないから、いる」 という基準だと、家の物全てが必要な物になってしまいます。
したがって、「いつ使うか不明瞭な物」を必要品としたり、「もったいないから」という理由だけで残さぬように整理しましょう。
②思い出の物を整理する
とはいえ、どうしても手放せないものは出てきてしまうものです。
それが、思い出の品物です。
日常的に使えなくても、残しておきたい物をわざわざ捨てる必要はございません。「思い出箱」を作り、全て収納しておきましょう。
③貴重品を整理する
最低限、以下の貴重品は必ずひとつの場所にまとめておくようにしましょう。
・通帳
・保険、年金等の書類
・不動産、株式、債券、金融資産等の書類
・公共料金、インフラ関係の書類
・貴金属
・カード、印鑑
・その他契約書類 通帳、年金手帳、印鑑、保険関係の書類など
一度なくすと取り返しのつかないことにもなりかねません。
金銭に関わりのある物は全て貴重品として専用の箱を作成するのをおすすめします。
財産目録を作成する
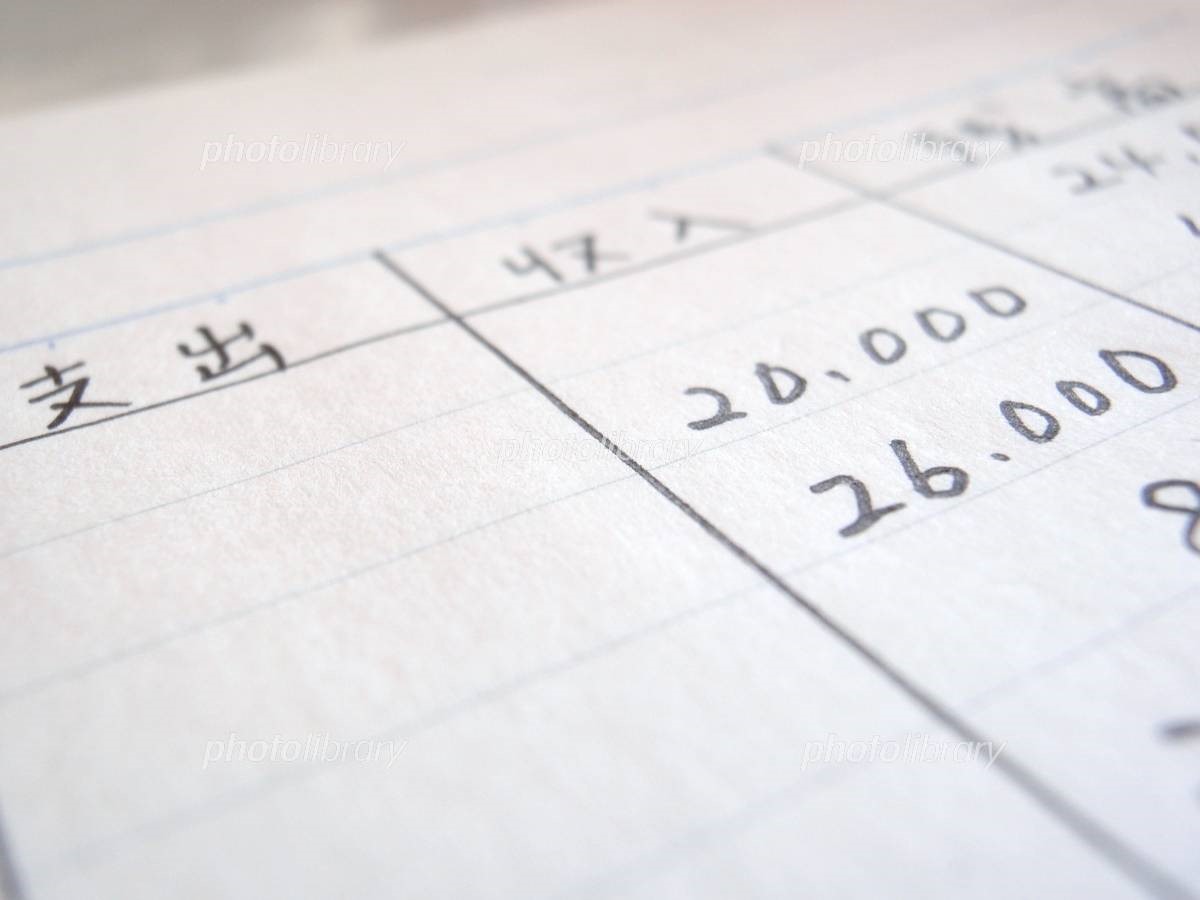
身の回りの物が整理できたら、次は「使う物」を「資産」と「負債」に分けていきましょう。 「財産目録」を作成し、それらを管理していきます。
①財産目録とは
死後、ご家族にどのような遺産を遺すのかをまとめた一覧表のことです。
不動産や預貯金、家賃や未払いの医療費など、相続すると決めた所有財産は全てこの表に記載します。
②財産目録を作る目的
最大の目的は「相続人が相続財産の全体像を把握するため」です。
亡くなられた後、複数の相続人で行われる遺産相続協議において、全ての財産を把握するのに使われます。
もし財産目録がなければ、相続完了後に新たな遺産が見つかり、トラブルの元になります。
公平な協議にするためにも、目録は必ず作成しましょう。
③財産目録の作成方法
「資産」と「負債」の2つに分類し作成します。
どの財産が資産もしくは負債にあたるかは、以下を参照してください。
これらを分類することで、遺産分割や相続放棄の判断をスムーズに行うことできます。
資産:不動産、預貯金、有価証券(株、FX)、自動車、投資信託、骨董品、家、宝石、美術品、貴金属
負債:住宅ローン、家賃、自動車ローン、未払いの所得税、固定資産税、住民税、未払いの医療費
④作成時の注意点
預貯金は口座ごとの残高を記載し、株式は銘柄や株式数など、数字や管理方法に応じて細かく区別してください。
金額の変化が大きい資産・負債ほど、細かく丁寧に整理するよう心掛けましょう。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
遺言書を作成する

遺言書とは「誰にどの財産を相続するのか」を明確に記載した文書のことです。
遺言書は「遺書」とは違い法的な文書です。日付、署名、捺印などがないと法的に無効になり、書式から作成方法までを正しいフォーマットで進める必要があります。
全ては残されたご家族が財産をめぐりトラブルを引き起こさないようにするためです。
遺書に記入できる内容は以下の通りです。
①推定相続人の廃除・廃除の取消
相続させたくない場合、家庭裁判所に申し立て、廃除が認められた際に記入します。
②相続分の指定・指定の委託
どの財産を誰に相続するかを記載します。
③特別受益持戻しの免除
「特別受益の持戻し」とは、特定の相続人が生前贈与を受けた分を「特別受益」とみなし、その分他の相続分を減少させることをいいます。免除の遺志を記載することで、特別受益を考慮せずに相続分が算出されます。
④遺産分割方法の指定の委託
「遺産分割方法の指定の委託」とは、遺言者が相続する遺産の内容を決めるのではなく、相続に利害関係を持たない第三者に委ねることです。
⑤遺産分割の禁止
相続開始以降5年間は、遺産分割を一切できなくする旨を記載します。
⑥遺贈
相続人以外の誰に財産を残すかを記載します。
⑦認知
内縁者(婚姻届を出していないが、夫婦として生活している人)との間にできた子供に遺産相続を希望する際、遺言執行者の届出をもとに自分の子供として「認知」することを記載します。
⑧未成年後見人・未成年後見監督人の指定
未成年の子供がおり、面倒を見る人が親族にいない場合、ご自身がお亡くなりになられた後の後見人を指定することができます。
⑨信託の設定
ご自身(委託者)の保有するお金や不動産などの管理や処分を、信頼できる人(受託者)に任せる旨を記載します。
⑩保険金受取人の変更
生命保険の保険金受取人を変更することができます。
このように、あらかじめ何を書くべきか把握しておけば、遺言書もスムーズに作成ができます。 ご家族と必要に応じてご相談の上、遺言書を作成してください。
不用品を整理する

遺言書が作成できたら「使わなくなった物」の整理に取り掛かりましょう。
「使わなくなった物」は処分を検討される前に「売る物」と「捨てる物」に分けると効率良く整理できます。
まず「売る物」ですが、「本当に廃棄で大丈夫か?」を検討してみましょう。ご自身では売れないと思っている物も、数十年と経過した物は高価買取が可能なケースもあります。
経年劣化で錆びてしまい廃棄を検討していたネックレスが、貴金属として買取ができるようになったケースもあります。
素人ではどうしても判別が難しく、知らず知らずのうちに有価物を処分することが後を絶ちません。 ご自身で検討されても判断しかねる場合は、一度専門家へのご相談をおすすめします。
また「捨てる物」ですが、処分は「ご自身で行う」と「業者に依頼する」の2通りがあります。
ご自身で行う
ご自身でゴミ収集車にゴミ回収を依頼することも可能です。その際、地域によってゴミ収集に関する対応が異なります。 詳しくはお住まいの市町村の自治体へご確認ください。
業者に依頼する場合
①不用品回収業者に依頼する
家具などの大型ゴミや、大量のゴミが出てしまった場合は、専門業者に依頼することもできます。
ご自身だけでは処分に何日もかかってしまうようなゴミも、不用品回収業者であれば2日以内で作業が完了するケースもあります。
ご家族が遠方にいらっしゃる方など、ご自身だけでは処分が難しい場合は検討しましょう。
②遺品整理業者に依頼する
ご自身が亡くなられた後の遺品などを回収してもらえるよう、専門業者への依頼が可能です。
亡くなった後の遺品や家財を回収してもらうときは、遺品整理業者に依頼します。
遺品整理は、選ぶ業者や部屋の間取りにより費用が変動しますので、相見積もりを取るなど、慎重に検討してください。
まとめ
生前整理は、ご自身が亡くなられた後に遺産相続のトラブルを避けるために行うものです。
だからこそ、整理をする適切なタイミングを把握し、順序通りに進めることが生前整理を行う上では大切です。
遺されたご家族が、ご自身の財産とともに安心快適な毎日を送れるよう、生前整理をぜひ検討してみてください。