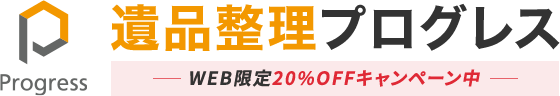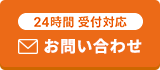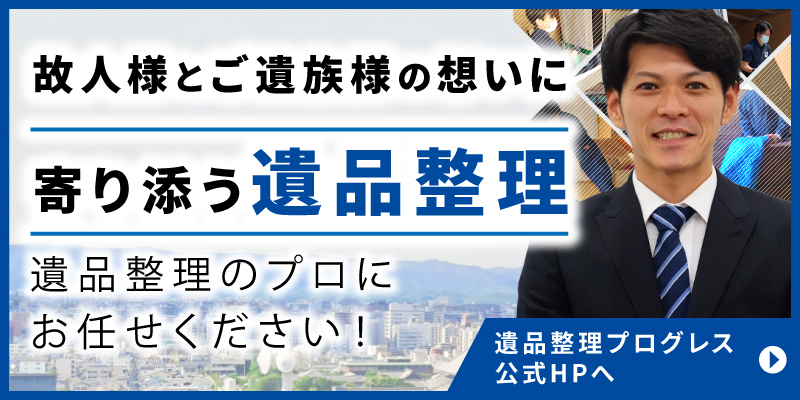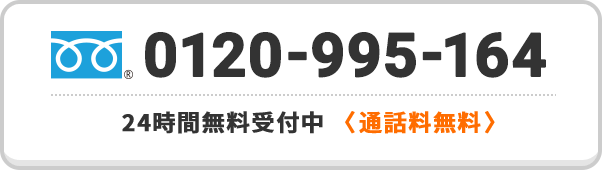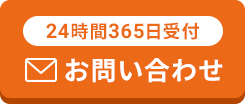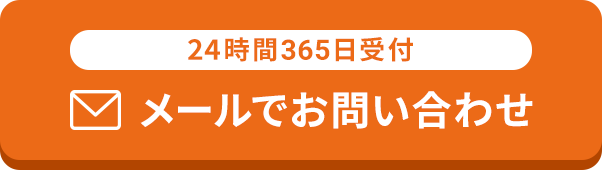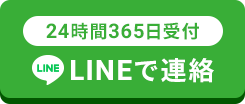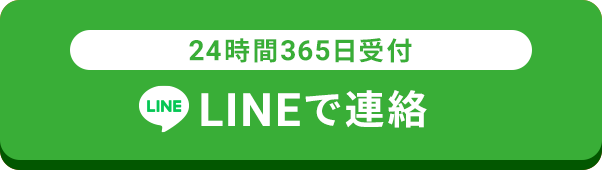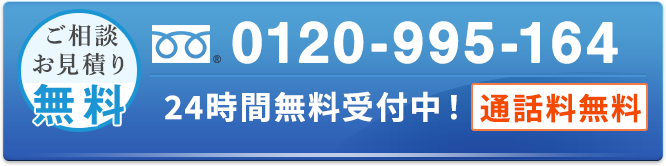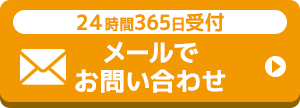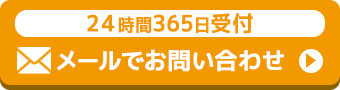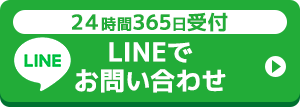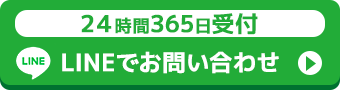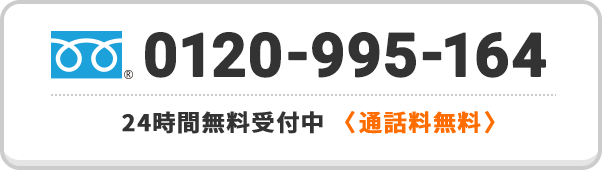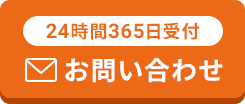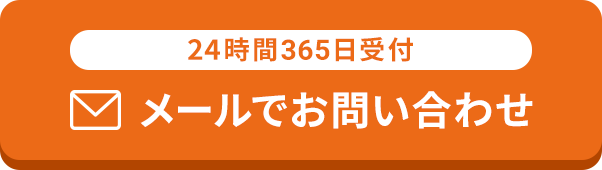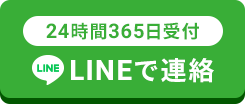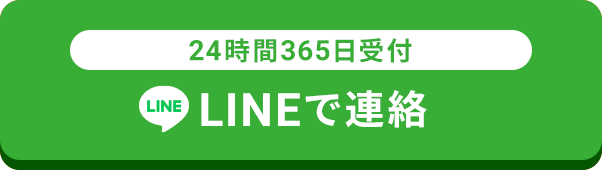誰もが経験しなければならない親の死ですが、覚悟していたつもりでも実際にそのときに直面すると動揺してしまい、何から手をつければよいかわからなくなってしまう方がほとんどです。
親が亡くなった後にやるべきことを事前に知り、流れを理解しておけば、もしものときでも慌てずに手続きを進められます。
今回のコラムを読み、死亡後の手続きの流れについて把握していただければ幸いです。
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
死亡届を提出する

ご家族が病院で亡くなられた場合、担当医師より死亡診断書が発行されます。
死亡届は市区町村に提出しなければならない書類です。
ご自宅で孤独死された場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。
死亡診断書の用紙の半分には、ご遺族が記入できる死亡届が付属しています。死亡届の欄に必要事項の記入と捺印をして、死亡を知った7日以内に故人の本籍地、もしくは届出人の住所地に提出しなければいけません。
また保険会社へ死亡保険金を請求する場合は、死亡届を提出する前にコピーをとっておく必要があります。死亡届は提出すると返却されませんので、複数枚コピーしておくと安心です。
葬儀の準備を始める

親族へ連絡する
死亡届の発行が終わった後は家族や親戚へ訃報の連絡をします。
親族であれば三親等までが連絡をする目安とされています。
親族への連絡が終わった後は、親しい友人や知人、勤務先にも連絡します。
訃報は亡くなった事実を取り急ぎ伝える連絡のため、葬儀の日程や式場などを具体的に伝える必要はありません。
人数が多く連絡に時間がかかりそうな場合は、友人や知人は葬儀日程や式場が決まり次第連絡しても問題ないでしょう。
葬儀の手配
遺体はしばらく病院で安置されますが、数時間後には別の場所へ移さなければいけません。
病院が紹介する葬儀社や故人が生前に契約していた葬儀社に連絡を入れ、遺体を別の場所へ移す必要があります。
自宅に搬送するか、自宅が病院から遠い場合は葬儀社の安置場に搬送します。
次に、葬儀社と葬儀の日程や場所、時間を決めます。
祭壇や仏花、供物、遺影の準備、精進落としの会食、火葬場までの送迎バスなどの手配など、大量に決めなければならないため、ゆっくり検討できないかもしれません。
筆者の祖母が亡くなったとき、喪主である父親は悲しむ暇がなかったと言っていました。 葬儀の準備や死亡後の手続きに追われるだけでなく、葬儀に参列された方への挨拶やお世話をしていると、あっという間に時間が過ぎてしまったそうです。
もし葬儀の準備や進行で疲れを感じたときは、無理をせず親族や葬儀会社のスタッフを頼りましょう。
葬儀の日程が決まったら、親族に連絡をします。家族葬を行う場合は決めた人だけ電話をかけるようにします。
火葬許可証の取得
役所で死亡届を提出すると、火葬許可証が渡されます。
火葬許可証とは文字通り、亡くなった人の遺体を火葬する許可が下りた証明書です。
お通夜、お葬式、火葬が終了すると火葬執行済の印が押された許可証が返却されます。これは後日遺骨をお墓に納めるときに必要になりますので、絶対になくさないようにしてください。
納骨は火葬直後ではなく、四十九日の忌明けの法要とあわせて行われます。印を押された火葬許可証を墓地や霊園に提出すれば納骨できます。
葬儀費用の支払いは、葬儀終了直後から1週間後に請求されます。
高額な費用が掛かりますが、すぐにまとまったお金を準備できない場合は分割払いも利用できます。
期限が短い手続きを終わらせる
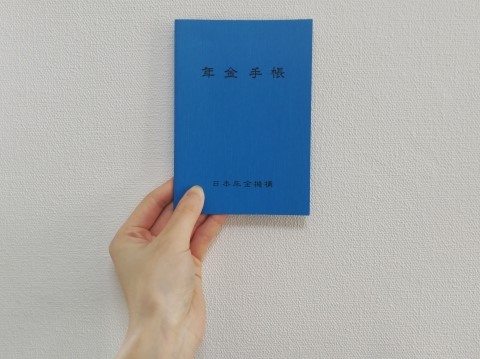
国民年金の受給停止、保健証の返却は死亡後14日以内に手続きを行わなければいけません。
年金の受給停止
年金を受け取っていた方が亡くなった後は、お住まいの地域にある年金事務所、あるいは年金相談センターに受給権者死亡届を提出します。
もし日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を収録していた場合は、受給権者死亡届の提出を省略できます。
受給者が死亡した後も年金を受給していると、不正受給となり刑事罰を問われる場合があります。
年金受給の停止、未支給年金の請求は忘れないうちに済ませておきましょう。
*参考サイト
保険証の返却
故人が国民健康保険に加入していた場合は、保険証を返却するための資格喪失手続きが必要です。
死亡から14日以内に、国民健康保険資格喪失届、国民健康保険の保険証、死亡届のコピーなどを故人の住所の市区町村役場に提出します。
故人が会社員であり、健康保険に加入していた場合は喪失手続きを勤務先で行います。
*参考サイト
銀行口座が凍結される前に費用を引き出しておく
口座主が死亡した場合、銀行口座は一時的に凍結されます。
口座が凍結されると口座から公共料金などの引き落としを一切行えません。
銀行は遺族からの連絡だけでなく、新聞や電報などで死亡した事実を確認して口座の凍結を行います。
口座主が死亡したことを銀行へ連絡しなくても罰則などはありませんが、相続手続きをするときに必要な相続人の印鑑証明書の有効期限は3カ月であるため、預貯金を引き継ぐ場合は早めに手続きをするようにしてください。
預貯金を引き継ぐためには、戸籍謄本、印鑑証明書などの書類が必要になります。
介護保険資格喪失届の提出
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護、要支援認定を受けていた場合は、死亡日から14日以内に介護保険の資格喪失届を提出します。
市区町村の役場によっては死亡届を提出するだけで介護保険の手続きが完了する場合があります。
介護保険被保険者証も返却するよう指示されない場合がありますので、事前に役場へ確認しておきましょう。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
期限がない手続きを終わらせる

電話や光熱費、賃貸物件の契約、プロバイダーの利用契約などは解約期限がありません。上記のするべきことがすべて完了してから、一つずつ解約手続きを行いましょう。
期限がない契約の例
・クレジットカードの契約
・NHKの放送受信契約
・証券口座
・介護ベッドなどのレンタルの契約
香典帳を作成すると便利
香典帳を作成しておくと香典返しや挨拶状を送る際に重宝します。
香典帳とは香典を誰にいくらもらったかを記録しておく帳簿です。香典帳には香典をもらった方の氏名、金額、住所、電話番号を記録しておきます。弔電や供花の有無も記録しておくと、頂いた物についてのお礼もお礼も選定しやすくなります。
故人の友人や仕事仲間など、ご自身とは直接関係ない人は故人との関係をメモしておくとスムーズにお礼ができるでしょう。
香典帳はノートに直接書いても構いませんが、最近ではパソコンやスマートフォンのアプリでも作成することができます。
頂いた香典袋は燃えるゴミとして処分して問題ありません。
筆者の父親は「思い切らないといつまでも手元に残してしまうから」と頂いた香典の金額が記録されているかを確認し、個人情報が見えなくなるよう裁断して処分していました。 もし罪悪感を感じてしまうのであれば、塩をかけて清めたり、お寺でお焚き上げをして処分しても問題ありません。
親が亡くなったときにしてはいけないことはある?
亡くなってから四十九日の忌明けまでの期間は忌中と言われます。
忌中は故人を偲んで過ごす期間として、賑やかな場所やお祝い事への参加を控えます。 お正月や新年会のお祝い、結婚式の参加は自粛しましょう。 また、神道では死は穢れと捉えられているため、神様が住む神社への参拝も避けるべきと考えられています。
相続についての手続きを終わらせる

故人に関わる手続きが完了した後は、遺産の相続手続きを行います。
手続きに不備がありトラブルが発生しないよう、事前に遺言書、相続人、相続財産を確認をしましょう。
相続人は民法で順位が決められており、配偶者は必ず相続人になります。そして第一順位が子供や孫、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となります。
もし親族以外の友人などに遺産を譲りたい場合は、生前に遺言書を作成しておく必要があります。
相続する物は財産だけでなく、借金などの負の遺産も含まれます。借金が見つかった場合は相続放棄ができます。
相続放棄の期限は3カ月以内なので、他の手続きと同様に忘れずに済ませてください。
借金を相続しないよう、生前に借主が返済をしたり、家族に伝えておくよう呼びかけておきましょう。
相続税の発生
相続する遺産が相続税の基礎控除を超えた場合は申告が必要になります。
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算できます。相続する財産がこの金額を超えていない場合は相続税はかかりません。
相続税を支払う必要があると判明した場合、申告するための書類を作成します。申告書以外の他にも、相続財産の資料、本人確認資料などが必要になります。申告書は税務署や国税庁のホームページから入手できます。
申告、納税は故人が死亡した日の翌日から10カ月以内に行わなければいけません。10カ月以内に支払わなければ延滞税が発生します。延滞税は期日を過ぎた日数分増加しますので、早めに支払うようにしてください。
相続性の申告書作成はあらゆる費用を計算しなければならないため、作成が難しければ税理士に依頼しましょう。
*参考サイト
まとめ
親が亡くなると悲しむ暇もなく、死亡届の提出や葬儀の準備、相続のための書類作成など短期間でやらなければならないことが大量に発生します。
今回は簡単にご説明しましたが、当日にもし混乱してしまっても、葬儀社のスタッフが案内してくれますので心配する必要はありません。
もしもの時に備え、葬儀の流れについてこの機会にご家族とお話をされてみてはいかがでしょうか。