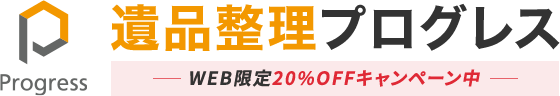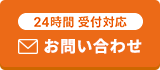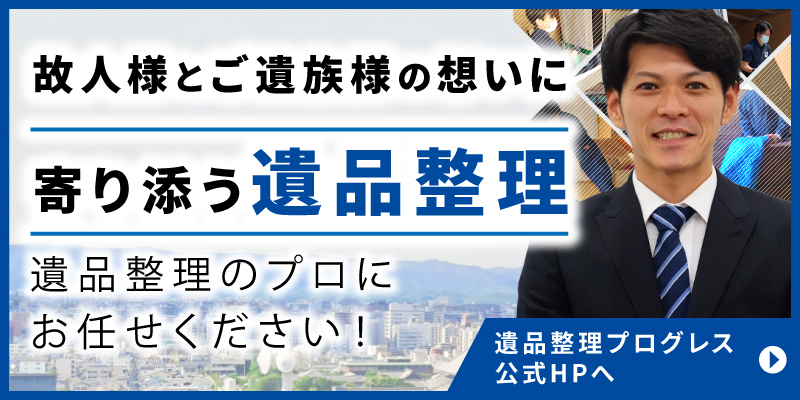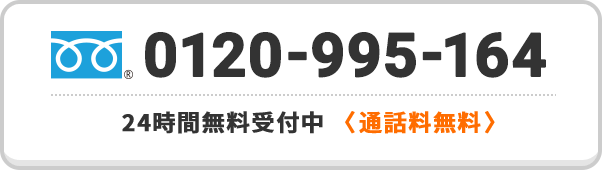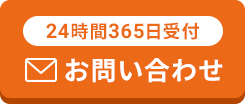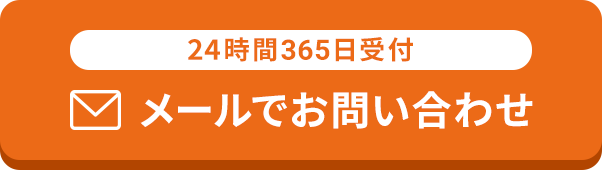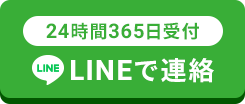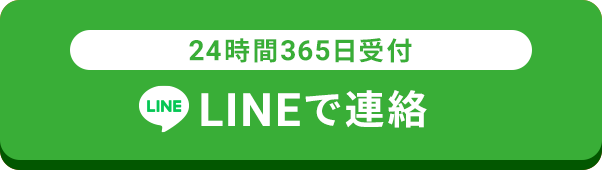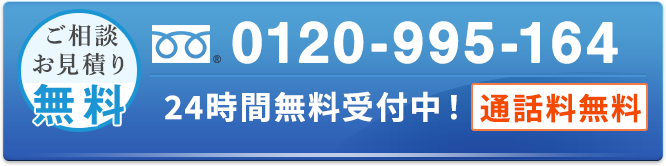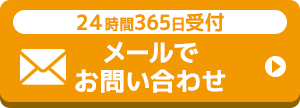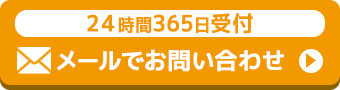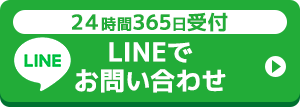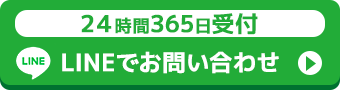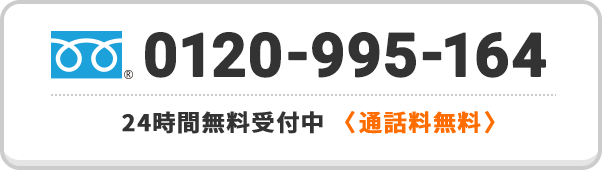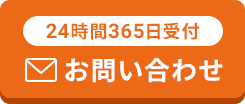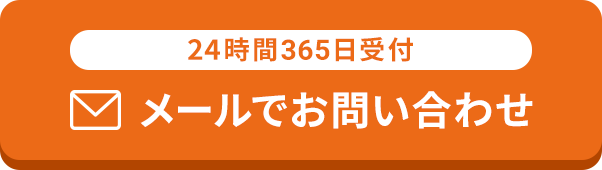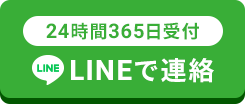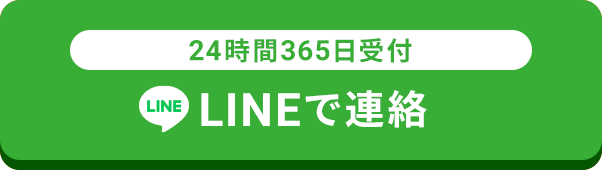大切な家族を亡くした後にはその方が愛用していた品々が残ります。身の回りの物から机やソファ、タンスなどの家具や家電類はもちろん、保険や税金、遺産相続に関する諸手続きまで様々な物を整理・処分しなければならず、想像以上に負担が大きくのしかかる作業だということを理解して取り組まなければいけません。
ご遺族様だけで進めるのが困難な場合も起こり得るため、遺品整理業者への依頼もあらかじめ念頭に入れておきましょう。
今回は、ご家族がお亡くなりになった後の実家の遺品整理の進め方について詳しく説明していきます。
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
親の死後、どのように遺品整理を進めるべきか

親が亡くなり四十九日の法要が終わる頃から遺品の整理を行う方が一般的には多く見受けられます。
実家の遺品整理をどのように進めるべきか、その手順を確認してみましょう。
①同居家族の有無によって進め方は異なる
同居家族の有無や持ち家か賃貸住宅かなど、故人の生活様式によって遺品整理の進め方は異なります。同居の場合は急いで整理を進める必要がなく、気持ちの整理ができてから着手しても問題ありません。
実家を手放すのか、それとも新たに活用するのかを決めてから遺品整理に取り掛かるようにしましょう。
しかし、故人が一人で暮らしていたのであれば、家が無人になるため早めの遺品整理をおすすめします。
空き家となった実家に遺品を置きっぱなしにしていると、不審者による不法侵入や盗難、放火などのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
また、故人が賃貸住宅に一人で住んでいた場合も、家賃の支払日までに退去を済ませなければいけません。 退去が遅れて不要な家賃や延滞金などを支払わないよう、できるだけ早く遺品整理を終わらせましょう。
②遺品整理は兄弟や親族など相続人が基本的に行う
親の遺品を整理するのは基本的に子どもや孫などの相続人です。相続を放棄する場合は遺品の整理に携わらないようにしなければなりません。
遺品は形見分けや相続する物と処分する品を分けながら整理しなければならないため、家族や兄弟、親族が一同に集まる四十九日などの法要の際に話し合いを行ってスケジュールを調整するとよいでしょう。
親の持ち物を整理するときの進め方

ほとんどの方が遺品整理をどのように始めるかわからないと思います。要点だけを整理しておきましたので、ぜひご参考にしてください。
遺品整理をする前に注意すること
①まずは心の整理を
悲しみに打ちひしがれて精神的に辛い状態のまま始めてしまうと思うようには進みません。いつかはやらなければいけませんが、ある程度心の整理が付いてから始めるようにしましょう。
②遺言書と相続財産に該当するものを確認する
遺品整理を進める前に遺言書と相続財産に該当する物があるかどうかを確認します。
故人の机の引き出しや棚、金庫など重要な書類を納めているような場所を探してみてください。最近はパソコンやスマートフォンの中に取引記録が保管されている場合もあるため、ロックの解除や操作方法が困難な場合は専門の業者に相談する必要があります。
相続人全員が集まれるときに捜索すれば、相続トラブルを回避できます。
■相続財産の一例
・現金
・預金通帳
・株式、債券などの有価証券
・生命保険証券
・土地や建物などの不動産
・金、宝石、高級時計など
・年金手帳
・骨董品や絵画などの芸術品
③多額な相続財産の場合は相続税が発生する
相続財産が高額な場合は相続税が発生し、死後10カ月以内に納税しなければなりません。
相続税はプラスの財産(預貯金や土地)から非課税の物やマイナスの財産(債務・葬儀費用など)を差し引いた総額で計算されます。
相続税が掛かるのは基礎控除額を超えた場合で、相続する額に応じて税率や控除額は違います。不明な場合は税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
遺品整理を行うときに注意すること
①整理をする範囲(部屋)を決める
「まずはこの部屋から」というように整理する範囲を決めて順番に進めていくようにしましょう。範囲が広い場合は部屋やフロアの担当場所を決めて、それぞれが責任を持って取り掛かります。処分の基準を定めて全員が共有していれば、別々に整理をしてもトラブルが起こらずスムーズに進められます。
②処分方法に応じて分別する
遺品整理では手元に残す物、形見分けする物、処分する物の3種類に分けます。処分する場合もリサイクルショップや専門業者に買い取ってもらえる場合もありますし、一般ゴミでは処分できず専門の業者に回収を依頼する物もあるなど、品物ごとに処分方法は異なるはずです。
処分する物を一括りにしてまとめて置くのではなく、処分方法に応じて分別するようにしましょう。
遺品整理のポイント

コツさえしっかりと把握していれば、実家の遺品整理をスムーズに進められます。
①処分する物は相続人全員で確認する
勝手に遺品を整理してしまったがゆえに家族間でトラブルに発展する事例は少なくありません。
必ず相続人全員で整理を行うようにし、処分する物を皆が把握するようにしてください。
処分品をまとめたら残しておきたい物がないか相続人全員で確認しましょう。
②整理スケジュールを立てる
細かいスケジュールを立てる必要はありませんが、全員が集まれる日やいつまでに終われせるかを明確にしましょう。また、想定外のことが起こり得るため予備日なども考慮し、余裕を持って日程を調整しておくようにしましょう。
予定を明確化しておきたい事項は下記の通りです。
・整理日と作業の期限
・整理する品物や部屋の順番
・ゴミの収集日
・ゴミの持ち込み場所(自治体のゴミセンター)と営業時間
・処分に掛かる費用の見込み
③分別スペースを確保しておく
仕分けた後にすぐ処分できるわけではないため、処分する品物を置くスペースの確保が必要です。
明らかに処分する物は家の外に置いていても問題ありませんが、それ以外は家の中で保管しなければならないため置き場所専用の部屋を決めるなど、前もってスペースを準備しておくとスムーズに整理が進みます。
④思い出の詰まった品物も思い切って処分する
写真や日記、ビデオなど故人の思い出が詰まった品物はなかなか処分しにくいと思います。
筆者も亡くなった祖母と撮影した写真や手紙を手放せず、引き出しの中に入れたままにしています。
亡くなった方との思い出の品物が少ない場合は、無理にすべて処分しなくてもいいと筆者は考えています。 思い出の品物は無理に処分せず気持ちが落ち着いてから少しずつ進めるとよいでしょう。写真に撮ってデータで保管したり、段ボール箱一つ分に収まるようにして手元に残したり、それぞれの思う方法で整理するのが一番です。
もし写真やアルバムを処分する場合は、供養をせずに可燃ゴミとして処分しても問題ありません。誰かに顔を見られたくない場合は、破ったりシュレッダーにかけてから処分しましょう。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
誰も住まない実家はどうするべきか?

親が亡くなった後で実家が空き家になってしまう場合は、遺品整理を進める前に家をどうするか決める必要があります。
①空き家になる場合はどのように管理するのか
国土交通省が令和4年10月に発表した「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」によると、二次的利用や賃貸用、売却用を除く長期にわたって人が住んでいない住宅は2025年には420万戸、2030年には470万戸に増加すると推計されています。
*参考サイト
実家が空き家になる場合、建物が良好な状態を維持するためには丁寧な管理が望まれます。
筆者は月に一度、空き家となった実家に戻り、庭の手入れや雨漏り・カビの確認、残置物の整理などの手入れをしています。他の用事によってどうしても空き家に戻れない場合は、親戚に相談して代わりに手入れをお願いしています。
ご自身が遠方に住んでおり、管理が困難であれば近くに住む知人、親戚もしくは空き家管理サービスを請け負っている業者に依頼するなどの措置が必要になるでしょう。
②売却する
不動産の名義が故人の場合は売却前に相続登記(不動産の名義変更手続き)を行います。
相続登記には2~3カ月を要するため、売却を検討している場合は早めに手続きしておきましょう。
不動産会社、もしくは遺品整理の専門業者でも不動産売却を請け負っているところがありますので、ご遺族様にとって最適な業者・方法を選定するようにしてください。
③他の方法で活用する
家も丈夫で便利な場所であれば賃貸として貸し出すことも考慮してはいかがでしょうか。
また、リフォームをしてゲストハウスにしたり、一旦更地にしてから駐車場にしたり、さまざまなオプションも考えられます。
不動産会社や活用方法に関する提案やサービスを請け負っている遺品整理の専門業者などに相談してみましょう。
実家の遺品整理を専門業者に依頼する

身体的に辛い場合や遺品整理をする時間がなかなか取れないという方は、遺品整理業者への依頼をおすすめします。
①遺品整理業者の仕事
遺品整理業者は遺品の仕分けや不用品の引き取り、部屋の清掃を請け負ってくれます。
荷物の整理だけではなく行政や各機関への手続きの代行など遺品整理に必要なほとんどの作業を行ってくれるため、人手や時間が不足している場合は依頼を検討してみるとよいでしょう。
遺品整理を専門にしているため遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧に遺品を仕分けて整理してくれます。
また、貴重品の捜索や、パソコンやスマートフォンなどのデジタル遺品に関するトラブルにも精通しており、個々の要望や相談に応じてサポートしてもらえます。
②安心して依頼できる遺品整理業者とは?
国民生活センターでは遺品整理サービスの利用を検討している方に向けて、以下のような注意喚起が行われています。
・複数社から見積もりを取るなど、事業者の選定は慎重に行う。
・作業内容や費用を明確に出してもらうなど、見積書の内容を十分に確認する。
・料金やキャンセル料、具体的な作業内容について事前に確認する。
・残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておく。
・事業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談する。
ご自身の判断だけでなく、利用者の声や感想にもよく目を通しておいたほうがよいでしょう。
また、不用品の買取には古物商許可、廃棄物の運搬には一般廃棄物収集運搬許可が必要になるため、それらの許可証を得ているかも確認してください。
*参考サイト
【「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル-料金や作業内容に関するトラブルが発生しています-」国民生活センター】
まとめ
遺品整理は人生のうちでもそう多くは経験しないでしょう。親の死後に実家の整理をどう進めるのか悩んで心配になるのは当然です。
遺品整理は相続問題にも関わりトラブルの原因ともなる大変な作業なので、相続人全員が集まって進めるのが理想です。まずはご遺族で話し合いながらスケジュールを立て、当コラムで紹介した遺品整理のコツや手順を参考に悔いの残らない遺品整理を行ってください。