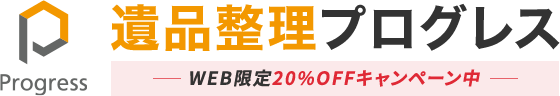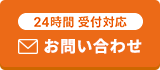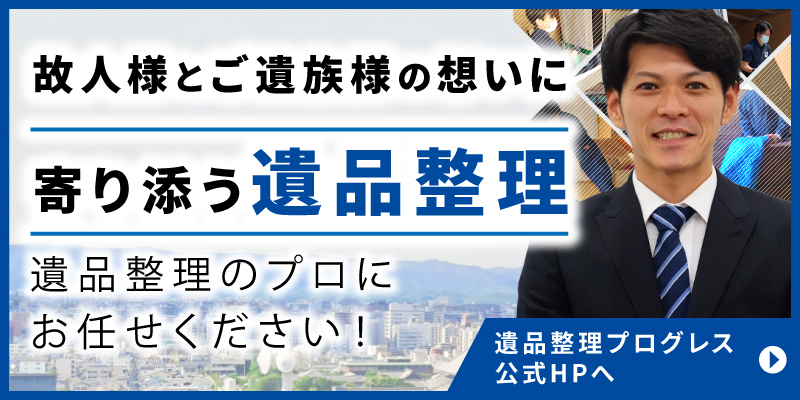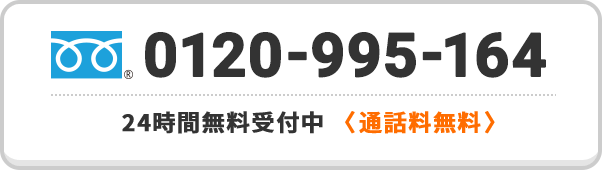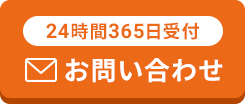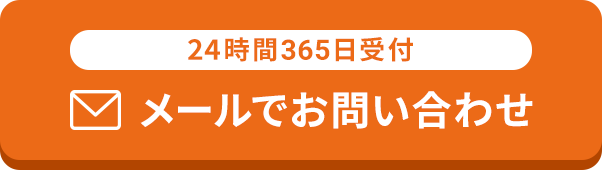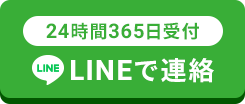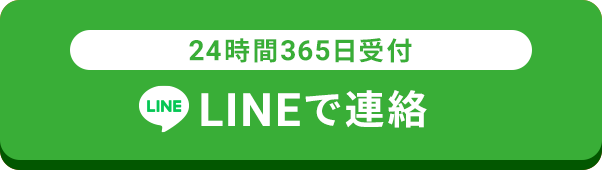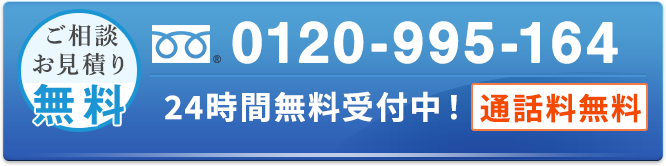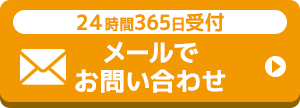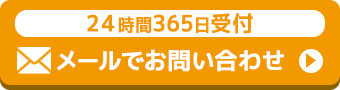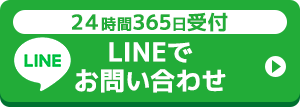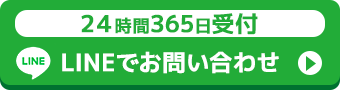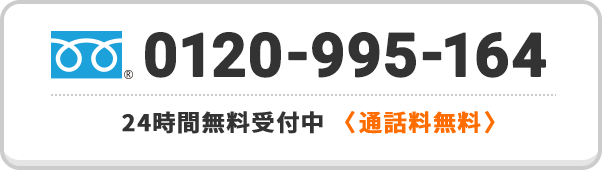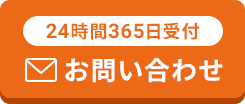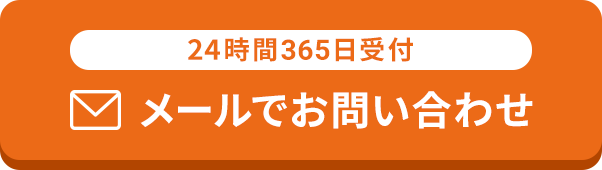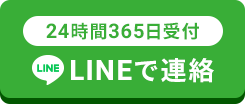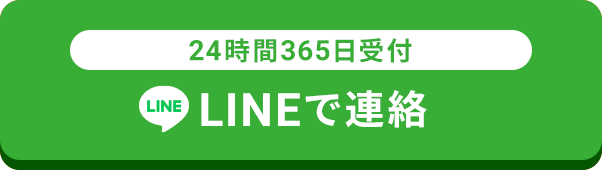遺品整理は親族一同が集まる四十九日の間が始める目安だと言われています。けれども形見分けが遅れて親族に迷惑を掛けないよう、四十九日よりも早く遺品を片付けたい場合もありますよね。
今回は四十九日前に遺品整理を行うメリットや、四十九日前に遺品整理を行っても問題ないのだろうかという疑問について詳しく解説いたします。
この記事を監修した人

- 小西 清香
- 整理収納アドバイザー
元汚部屋出身の整理収納アドバイザー。夫の身内6人の看取りや介護をし、生前整理の大切さを痛感。
また看護師時代ICUに勤務し、人の最期もたくさん見てきました。
そんな経験を元に元気なうちから生前整理を!という思いで、片付けと合わせてお伝えしています。
四十九日前に遺品整理をしても問題はない?

人は死亡すると四十九日間は現世をさまようと考えられており、故人が極楽へ旅立つ四十九日に法要が行われます。
遺品整理を四十九日の間に済ませるべきだと言われる理由として、故人が心残りのないようあの世へ旅立てる支度をするためと言われています。
親族間で同意が取れていて心の整理がついているのであれば、四十九日前に遺品整理を行っても問題ありません。
市役所へ返納するべき書類や公共料金の納付書など、期限が決められている物が後ほど発見される可能性もありますので、なるべく早い遺品整理を心掛けましょう。
しかし、大切な人が亡くなったショックは大変強く、数日程度では消えない場合も十分に考えられます。気持ちの整理がつかないうちに遺品整理に取りかかっても、必要な物と不必要な物をうまく判断できないまま、十分な整理を進められません。
大切な方が亡くなった直後はゆっくりと時間をかけて事実を受け入れるべきだと筆者は考えています。
親戚や家族に喪失感やつらい気持ちを打ち明けるだけでも心が軽くなりますので、悲しみから立ち直れるように感情は我慢せず表に出しましょう。
そして気持ちの整理をつけてから遺品整理を始めましょう。
四十九日前に遺品整理を始めるときの注意点

四十九日前に遺品整理を行う場合は、必ず配偶者や喪主を含む相続人全員から承諾を得て始めるようにしましょう。
亡くなった直後に遺品を片付けると、「故人との思い出の品に関心がない」と悪い印象を相続人に与えてしまう可能性があります。
遺品整理を行う際、優先的に取り掛かりたいのが「重要書類や個人情報に関する物の捜索」です。保険証や年金手帳の返納、公共料金の支払い手続きなど、死亡後速やかに手続きをしなければいけない書類はすぐに処理をしましょう。
反対に急いで整理すべきでない物は、故人の写真や生前大切にしていた趣味の道具です。
どうしても故人を思い出してしまい、精神的に辛くなったり、判断を誤って処分してしまう可能性があります。遺品整理の時に思い出の品を入れる箱を用意し、気持ちが落ち着いてから仕分け作業や供養をしましょう。
四十九日前に遺品整理をするメリットとは?

故人が死んでから間もない四十九日前に遺品整理をすれば、金銭的なデメリットも回避できます。
遺品整理の際に見つけた支払いの明細やエンディングノートから、生前は把握しきれていなかった請求(サブスク利用など)の存在に気付き、解約をすれば利用者がいないまま金額を支払い続けるのを素早く防止できるためです。
反対に、遺品整理が大幅に遅れてしまうと公共料金や月額利用サービスの支払明細書に気付かず、不要な料金を支払わなければならなくなります。 さらに、遺品整理をすれば相続税を算出しやすくなります。
国税庁のホームページによると、相続税申告書の提出期限は被相続人の死後10カ月以内と定められています。 この期限を過ぎると税金の控除を受けられなくなるだけでなく、延滞税を支払わなければなりません。
*参考サイト
相続税を算出するためには被相続人の土地、不動産を洗い出さなければいけませんので、死後10カ月以内に遺品整理をして税金が発生する財産を明朗にしておく必要があります。 遺品の価値を調べて明確にしておけば、親族間で形見分けを比較的スムーズに行えます。
四十九日法要は親戚が一堂に集まるタイミングですので、それまでの間に、できるだけ早い段階で相続すべき遺産や遺品を把握すれば遺品相続、遺産分配に関するトラブルも回避できます。
プログレスは全国の
エリアで展開中!
現状対応できない地域も一部ございます。
詳しくはお問い合わせください。
四十九日が終わるまでしてはいけないことはある?
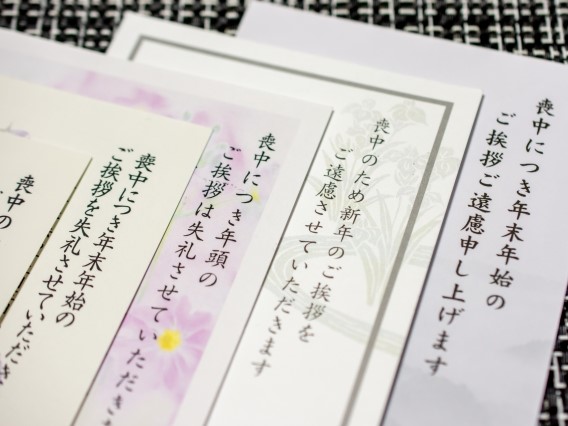
四十九日前に遺品整理を済ませれば、四十九日中は法要と納骨式を除けばあとは普段通りの振る舞いをしてもよい気がしますよね。
ですが、以下の行動は周囲に悪い印象を与えてしまう恐れがありますので慎むようにしておきましょう。
お祝い事に参加する
結婚式や七五三など、華美なお祝い事は避けるべきだとされています。参列を辞退、あるいは日程をずらし、後日お祝いの言葉を贈るなどをして祝福しましょう。
七五三は神社で行いますが、神社によっては喪中の七五三を避けるべきだと考えられています。
東京神社庁では父母が死去した場合、50日は神社参拝を遠慮するべきと紹介されています。
*参考サイト
もし気になる場合は神社へ相談したり、喪中開けに行えるよう日程を調整してください。
お中元やお歳暮
お中元やお歳暮はお祝い事とは違い、日頃の感謝を伝えるための品ですが、忌中の時期は贈らないほうがよいとされています。
お中元を頂いた場合は3日以内に忌中であると断りを入れ、お中元を頂いたお礼を相手に伝えるようにしましょう。
忌明けに入ってからお中元をお返しするようにしましょう。
また、相手が故人の訃報を知らない場合、故人の自宅へお中元が届いてしまう場合もあります。その場合は故人が亡くなったという連絡と、訃報の連絡を贈らなかったお詫びの気持ちを書き添えたお礼状を送るようにしましょう。
引越し、家の新築
故人の魂は四十九日の間は家にいると考えられています。そのため、故人の魂を遺したまま引越しや新居に移るのは避けましょう。
けれども以前より引越し業者へ依頼をしていた、退去日が迫っているなど、やむを得ない事情がある場合は家族で話し合い、同意を得てから故人の家を手放すようにしましょう。
引越しをした際は喪中はがきにも住所が変更したという旨を書き添えます。
遺品整理業者の利用がおすすめ

遺品整理を行うタイミングや時期に決まりはありません。
ですが、四十九日前後は親族とのやり取りや心のケア、諸手続きなどで忙しく、遺品整理まで手が回らない場合もあるでしょう。
筆者の祖母が亡くなったときは、葬儀を手伝ってくれた方への挨拶や、香典返しの手配などに追われ、遺品について考える余裕がありませんでした。 後日、大量の遺品整理に頭を抱えることになったため、遺品整理を誰かに委託するべきだったかもしれません。
故人の自宅に大量の残置物や特殊清掃を施さなければならない汚れが残されていた場合は、近隣の住民へ悪臭などの二次被害を及ぼしてしまうため、通常よりも速やかにゴミの撤去、清掃を行わなければいけません。
計画通りに遺品整理が行えそうにない場合は、遺品整理業者の利用もおすすめです。
最近は部分的に作業を依頼できる業者もあり、上手に利用すれば金額を抑えながらもスムーズに遺品整理ができます。
業者に依頼する際には、遺品整理士の資格を持った業者を選びましょう。 遺品整理士は通常の不用品回収者とは違い、大切な人を亡くした遺族の気持ちに寄り添って遺品の整理、供養を手伝ってくれます。
また、豊富な経験とノウハウを持っているため、誤って重要書類を捨ててしまうといったトラブルを防止できます。 遺品整理業者の中には立ち会いなしで作業を行ってくれる業者も存在しますので、現場を一旦離れなければいけなくなったときに便利です。 ネットで遺品整理業者を検索するとたくさんの業者が出てくるかと思います。そしてその中には悪徳業者も含まれます。
利用前の見積もりではサービス内容や料金だけを確認するのではなく、スタッフの服装や対応もチェックしておくと優良な遺品整理業者を見分けられます。問い合わせや見積もりは無料で対応してもらえる場合がほとんどのため、実際に依頼をして雰囲気や相性を見極めるのがおすすめです。
まとめ
親族が集まり、今後について相談する機会が増える四十九日前はまさに遺品整理に適した時期だといえるでしょう。
早急に遺品を片付けなければならない場合、四十九日前に遺品整理を初めても問題ありません。
しかし、大切な人が亡くなった事実を受け入れられていないと、手元に残す遺品と捨てる遺品の区別がはっきりと判断できない可能性があります。
悲しみで遺品整理がうまく進まない場合は、ご自身の気持ちが落ち着いてから再開しましょう。